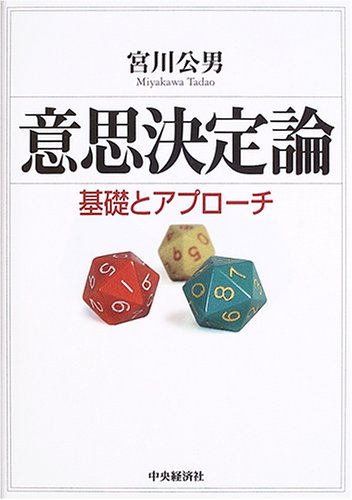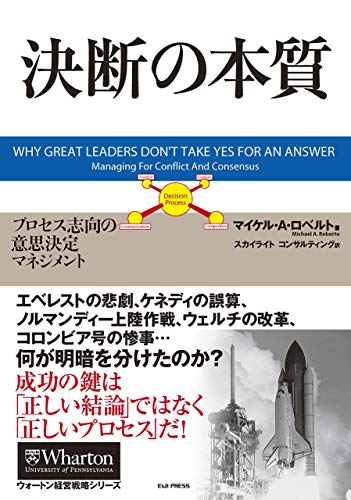部下の意見がいつも対立する。せっかく企画を立案しても、内容の吟味よりも利権の調整めいたプロセスに時間が取られてしまう。マネジャーの持ち時間の多くは、何らかのコンフリクト(葛藤・対立)の解消に費やされます。あるマネジャーは、自分の仕事を「組織の水道屋」と呼んでいました。そのこころはもちろん、組織の上下・左右の「流れを良くすること」が仕事だから。
コンフリクトに対処するための、さまざまな方法論が提唱されています。今回は対処の前段の部分、コンフリクトの所在を明らかにすることについて考えてみます。
●「どこで」「どんな」コンフリクトが起きているのか
まず、組織におけるコンフリクトのレベルを切り口に考えることができます。意思決定のすぐれた総説である『意思決定論―基礎とアプローチ』で、著者の宮川 公男はコンフリクトの古典的な分析アプローチを紹介しています(1)。
たとえばマーチおよびサイモンは、コンフリクトを(1)個人的コンフリクト、すなわち個人の意思決定におけるコンフリクト、(2)組織内コンフリクト、すなわち組織における個人間およびグループ間コンフリクト、(3)組織間コンフリクトの三つに分類し、そのうちの(2)を中心的な考察対象としている。
これは、言ってみれば「どこで」コンフリクトが起きているのかを考えることです。「どこで」とくれば、次に知るべきは「どんな」コンフリクトが起きているのかでしょう。これにもいくつかのアプローチがありますが、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・A・ロベルト教授は、感情−認知という切り口を分析の起点に据えています。
具体的には、感情的コンフリクトの高−低を縦軸に、認知的コンフリクトの高−低を横軸にしたクワドラント(2×2のマトリクス)を描き、今起きている対立がどの象限に入るかを評価します。そのうえで、感情を排除するのではなく効果的にマネジメントすることを意識しつつ、コンフリクト解消のプロセスを設計していきます(2)。このような分析によって「一拍置く」こと自体に意味があります。「6秒間で思慮深さを取り戻す」という回で紹介したように、感情を言葉にするなど自分の感情を認知する活動そのものが、興奮を鎮める効果を持っているからです。分析の基本は「分ける」ことですから、コンフリクトを感じたら、まずは淡々と「どこで」「どんな」コンフリクトが起きているのかを分けて観察してみるのがよいのではないでしょうか。
●大きな目的に立ち戻って、コンフリクトを評価し直す
そのようにして掘り下げていくと、大きなコンフリクトの原因に「個人的な」かつ「感情的な」コンフリクトが横たわっていることが少なくありません。わたしが遭遇した忘れがたいケースを紹介します。
講師を務めたある教育プログラムの参加者の中に、とても熱心に論理的思考を学ばれているAさんがいました。講義の最中はもちろん、講義後にも講壇までやってきて質問をしてくれます。思考法を学ぶ人の中には、しばしば「お勉強」そのものが好きで、実務への応用には熱心でない人もいますが、Aさんはそうではありません。非常に具体的なシーンを想定しておられることがうかがえました。
Aさんの興味はつねに「組織的な」かつ「認知的な」コンフリクトの解消にあるように思っていたのですが、実はそればかりではなかったのです。親しく話をするようになって、Aさんの学習の動機が社内の特定の人物(以下Bさん)への敵愾心にあることに気づきました。AさんとBさんは職種が違うので、いまの職位では出世競争の相手というわけではありません。しかし利害が衝突しがちな部署にいて、ともに頭の良さを武器にしていることがうかがわれます。ほかに個人的な事情もおありだったかもしれませんが、なんとかしてBを論破してやりたいという思いの強さは、聞いていて驚くほどでした。
Aさんには「自部署対他部署(Bさんの部署)」という構図だけに注目せず、つねに社外のエンティティ(顧客・競合企業・大手輸入元など)を視野に入れたうえで部署間のコンフリクトを考えるようにアドバイスさせていただきました。当たり前のようですが、Bさん憎しの気持ちが強かったAさんは、新しい商品をひとつ出すのにも、まずBさんの部署をどう説き伏せるかという点に考えが向かってしまっていたのです。
(1) 宮川 公男 『意思決定論―基礎とアプローチ』 (中央経済社、2010年)
(2) マイケル・A・ロベルト 『決断の本質 プロセス志向の意思決定マネジメント』 (英治出版、2006年)