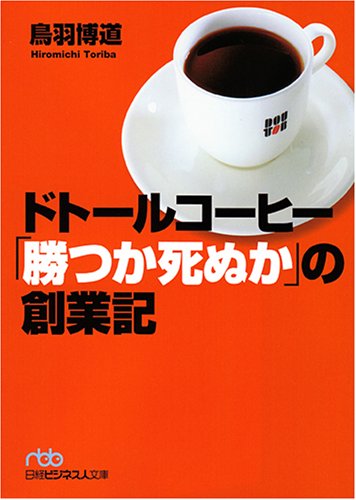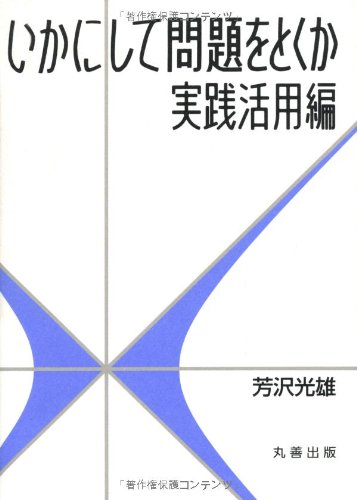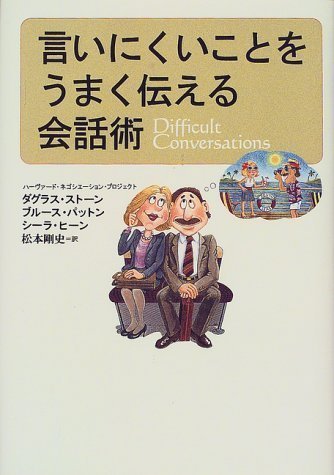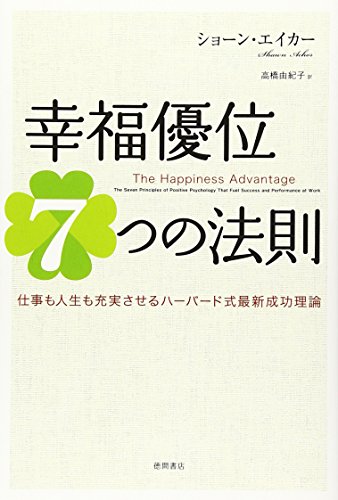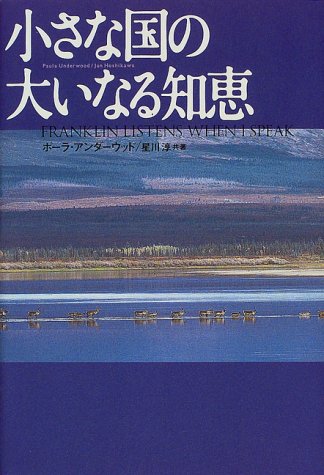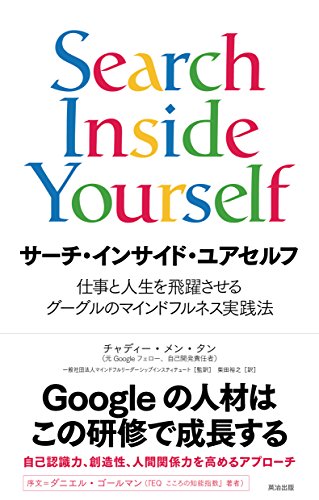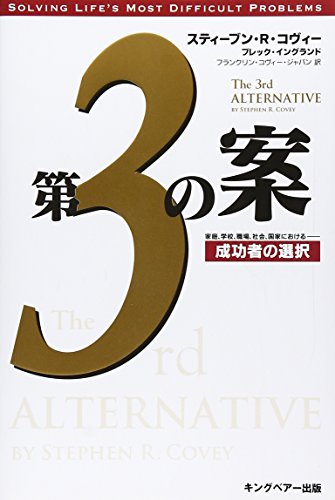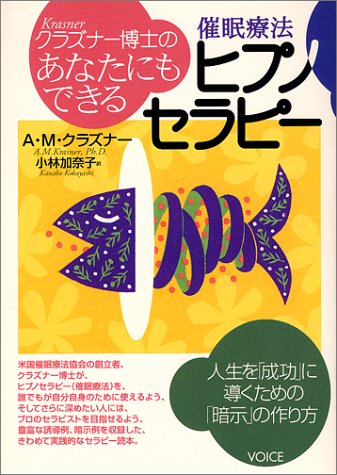ドトールコーヒーの創業者、鳥羽博道氏の『ドトールコーヒー「勝つか死ぬか」の創業記』という本に、印象的な箇所がありました(1)。
『ドトールコーヒーの発展成長は「一杯のおいしいコーヒーを通じて人びとに安らぎと活力を提供する」という喫茶業の使命をいかに高いレベルで実現できるかという点にかかっている』と考える著者は、コーヒーはもちろん、店の構成要素すべてを「安らぎと活力」という観点でチェックします。
スプーン、カップなどの什器・備品についても、安らぎと活力を与えるものはどういうものかという観点から選んでいる。たとえば、スプーンについては、これは男性好みになっていないか、若者好みになってないか、といろいろ考えて、三回ほどつくり替えたりもした。
安らぎと活力を与えるスプーンとは、どんな形なのか。興味が湧きますね。実はこの本をドトールコーヒーで読んでいたのですが、上記の箇所まで読み進めたときには店を出てしまったためにスプーンの形を思い出せず、悔しい思いをしています。少なくとも、思い出せない程度に自己主張のない、コーヒー体験を邪魔しないようなスプーンであることはたしかでしょう。
「一杯のおいしいコーヒーを通じて人びとに安らぎと活力を提供する」。この言葉を反芻していて、よい企業理念の要素をいくつか抽出できるように思えましたので、メモしておきます。
1. イメージしやすい
「安らぎと活力を提供する」。「安らぎ」も「活力」も、読み手が抱くイメージにそれほどブレがない一方で、時や場所によっての違いを盛り込めそうな、ほどよい抽象度の言葉です。これがたとえば「ドトールならではのサービスを提供する」や「新しい価値を創造する」だと、解釈の幅が広すぎて、結果的に「なんでもあり」になってしまいそうです。
2. せめぎ合う複数の要素が入っている
「安らぎと活力」はイメージしやすい一方、両立が難しい要素です。しかし、もし「安らぎ」だけを掲げてそれを追求していくと、安らぎが多ければ多いほどよいことになり、ゆるんだ店になりそうです。逆に「活力」だけでは、ギラギラした店になりそうです。両立しづらいものの両立をめざすことで、企業の方向が極端にぶれてしまうのを避けられるのではないでしょうか。また両立しづらいものの両立をめざす言葉は、永遠の課題を追いかけようという意味であり、企業が存続するかぎり掲げられるべき理念にふさわしい寿命を授かっています。両立させようという苦労の中から独自の価値が生まれてくるようにも思えます(2)。
3. 目的と手段の両方が入っている
安らぎと活力を提供しさえすればよいのであれば、アミューズメント施設でもよいことになります。目的だけが重要であれば、ドトールコーヒーは社名をドトールとしたうえで、企業理念を「人びとに安らぎと活力を提供する」としてもよいはずです。しかし目的は、具体的な手段とセットになって初めてイメージとなってわれわれの脳裏に浮かび、人を引きつけるものです。「安らぎと活力の提供」という目的を「一杯のおいしいコーヒー」でなしとげようというところに、人を一つにまとめる何かがあるように思います。
4. 自分・自社の成功よりも大きなものをめざしている
著者は「一杯のおいしいコーヒーを通じて人びとに安らぎと活力を提供する」ことをドトールコーヒーだけの使命とは考えていないようです。冒頭の引用文から読み取れるのは、それは「喫茶業」の使命であり、それも最も高いレベルで提供するのが我がドトールコーヒーだ、という意気込みです。
安らぎと活力を提供する対象が「お客さま」ではなく「人びと」なのも、よい言葉の選択だと思いました。収益事業だけでなく企業活動のすべてに理念を関わらせやすくなるからです。店頭にコーヒーの香りを漂わせることですら、「集客を仕掛けている」のでなく「街ゆく人びとに安らぎと活力を提供している」のだと考えれば、意義深く仕事に取り組めるでしょう(現在のホームページでは「人びと」が「お客さま」になっているので、ここは深読みしすぎているかもしれません)。
(1) 鳥羽 博道『ドトールコーヒー「勝つか死ぬか」の創業記』(日本経済新聞出版社、2008年)
(2) 『ビジョナリー・カンパニー』では「ANDの才能」として称揚されています。