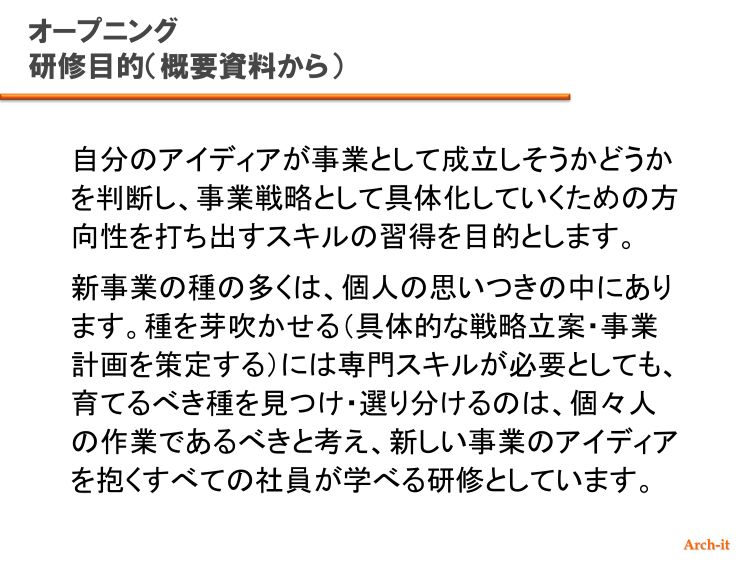投稿者: Koji Horiuchi
-
083 世界と自己と未来
●認知の3要素と戦略立案の3ステップ 精神科医で、うつ病の認知療法の創始者として認められている(Wikiped…
-
082 感情にかしこくないとはどういうことか
●組織で評価されない人の共通点 能力があっても組織で評価されない人には、どのような特徴があるのか。『残念な人の…
-
081 確信しているが、頑なではない
●増幅仮説 学術誌で「説得における、認知および感情の一致効果」(1)という論文タイトルを見かけました。素人が要…
-
080 “LJ”に聞いてみる
●自分に相談する 自分の問題や、考えたいこと、伝えたいことを再定義する。つまり、他者の視点から、あるいは一段深…
-
079 成功こそ成功の母?
●成功こそ成功の母 「失敗は成功の母」という言葉をバッサリ否定するような面白い文章を見つけました(…
-
078 過去に引きずられないためにも「選び直す」
●損失を嫌がるバイアスの源 EQ理論(Emotional Intelligence Theory)の提唱者とし…
-
077 やる気を見つけるために、現状を「選び直す」
「週末は、親戚の介護があるんですよ」 友人のAさんから、そんな近況を聞きました。Aさんの伯母は伴侶に先立たれて…
-
076 「意思決定日誌」の項目
投資家のマイケル・J・モーブッサンは、直訳すると『2度考えよ』と題した本の中で、自分の意思決定を改善する方法と…
-
075 意志決定の手本となる(あの人なら、どうするだろうか)
複雑な意志決定にあたって、「あの人なら、どうするだろうか」と考えてみると新たな視点を得ることができ…