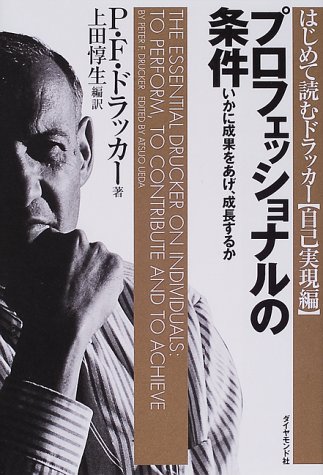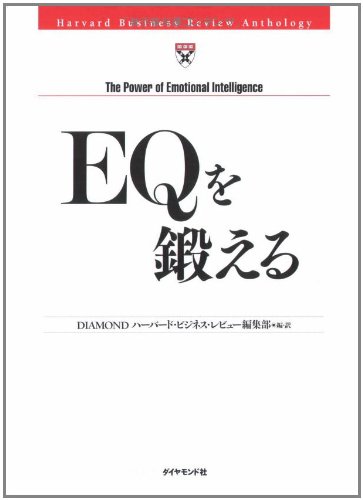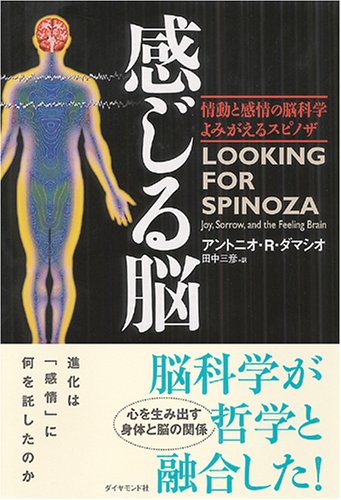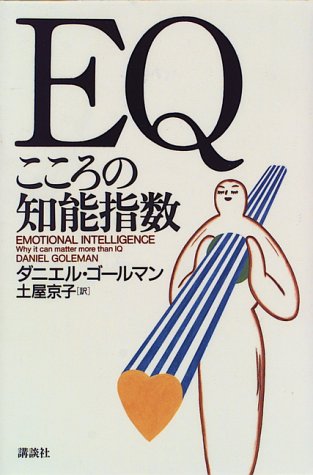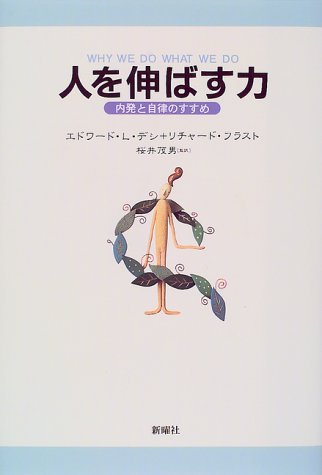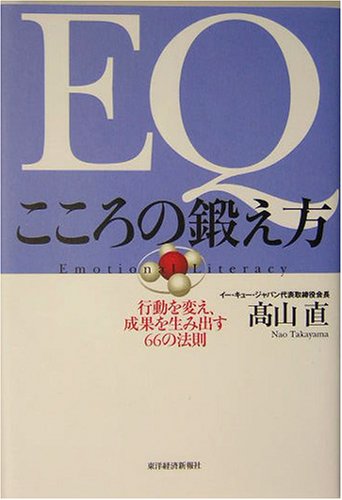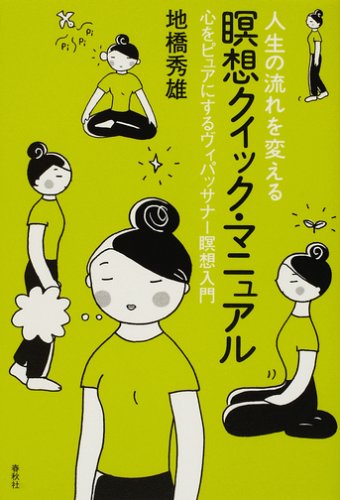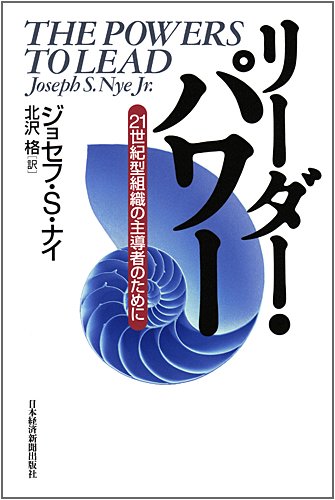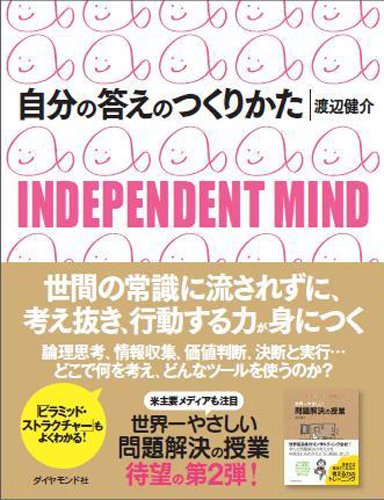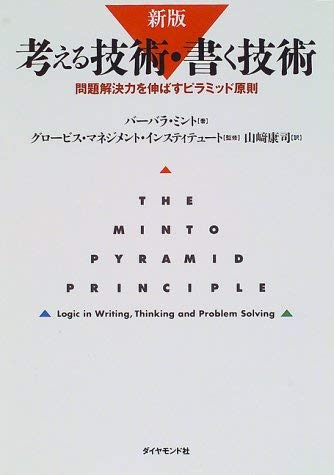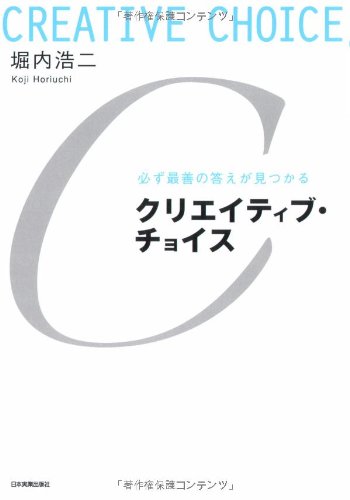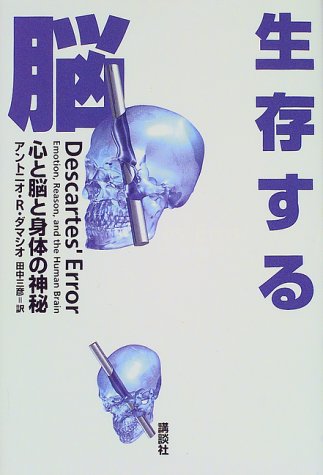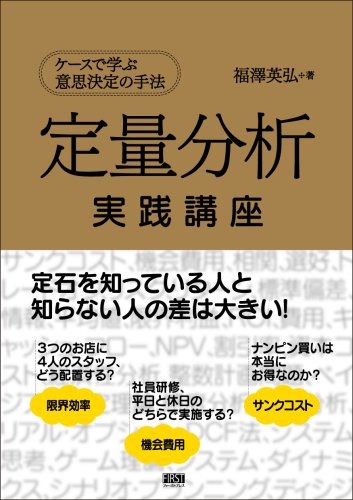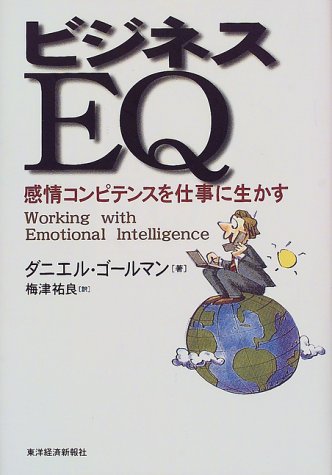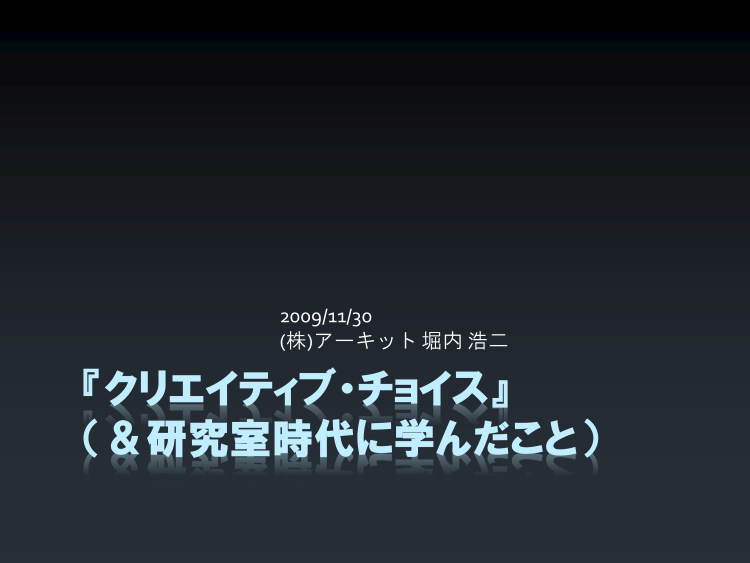ピーター・ドラッカーは、キャリアのどこかで「退屈」が生じる可能性を示唆しています(1)。
知識労働者には、いつになっても終わりが無い。文句は言ってもいつまでも働きたい。とはいえ、30のときには心躍った仕事も、50ともなれば退屈する。したがって第2の人生を設計することが必要になる。
問題は、われわれが「退屈」していることを感じ取れない、あるいは感じていても無視・抑圧してしまうことです。それは、社内での競争が忙しいためかもしれませんし、変化を自ら起こすよりは現状維持のほうが楽だと考えてしまうからかもしれません。
『EQ こころの知能指数』の著者ダニエル・ゴールマンは、2002年にHarvard Business Review誌に論文を投稿しています。『「燃え尽き症候群」を回避する自己管理術』と題されたこの論文に、「人生の棚卸しのタイミングを知る」という項がありました。自分の人生を見直すきっかけの訪れが、次の6つの「シグナル」としてまとめられています(2)。
- 「行き詰まりを感じる」 ― 仕事の目的を見失って焦りを感じるが、成功した人ほど「降りる」のが難しい。
- 「もううんざりだ」 ― 成功への野心や意志といった気質を持つ人ほど「うんざりしている」という事実を認識するのは難しい。
- 「いまの自分は自分が望んでいるような自分ではない」 ― 適応性に優れた人ほど、みずからが信ずるところに従う代わりに、小さな譲歩を何度となく繰り返してしまう。
- 「倫理をないがしろにしたくない」 ― みずからの正義と対立する事態に直面して、自分の人生を見つめ直す必要に迫られる。
- 「使命を放っておけない」 ― まるで突然の啓示を受けたかのように「それ」を無視し続けられない衝動にかられる。
- 「人生はあまりに短い」 ― 人生の節目で、これまでの選択の是非を自問自答したり、達成してきたことと夢とを引き比べてみたりする。あるいは突発的なできごとによって、自分にとって大切なことがはっきりとする。
人生を見直すきっかけとなる6つの「シグナル」 – *ListFreak
特に、1の解説文の中にはハッとする記述がありました。われわれの多くは、「行き詰まり」を感じたとしても、状況を打開するようなチャレンジを簡単にはできない理由があります。たとえば、社会的地位や経済的な面での生活水準など。しかしその帰結はどうか。著者はこう述べています(2)。
これらの理由から、状況が好転することを期待しつつも、疲れた足取りで同じ道を延々と歩まざるをえない。安定にしがみついたり、よき企業市民たらんと努力したりするが、結果的には自分で自分の牢獄をせっせと築くことになりかねない。
自分で自分の牢獄を築くとは、かなり厳しいコメントです。それだけ著者の危機感が大きいと読み取るべきでしょう。
ゴールマンは、そういった「シグナル」を感知してその意味するところを自分なりに解釈するために、いくつかの方法を提案しています。なかでもページ数を割いていたのが「内省」でした。特別なメソッドを学んだりする必要はありません。彼が提案していたのも、過去を振り返る、人生の基本原則を定義する、やりたいことを書き出してみる、15年後の生活を描いてみるなど、いわば「ありふれた」エクササイズです。
しかし、そういったありふれたエクササイズをやっていないことを知らせてくれるのが「シグナル」なのでしょう。ゴールマンは内省を促すために、先のような厳しいコメントを埋め合わせてあまりある、力強い応援メッセージを贈っています(2)。
つまるところ、その人生を早晩見つめ直す必要性が、ほとんどの人々に差し迫っている。内なる声に耳を傾ける機会に恵まれた人は、十中八九、これまでにもまして、強く、賢く、決意に満ちて、内省の時から戻ってくることだろう。
- P・F. ドラッカー 『プロフェッショナルの条件―いかに成果をあげ、成長するか』(ダイヤモンド社、2000年)
- DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部 『EQを鍛える (Harvard business review anthology)』(ダイヤモンド社、2005年)