EQ関連サービスを提供している企業の皆様に、たくさん勉強させていただいたお礼に1日研修をプレゼントしました。
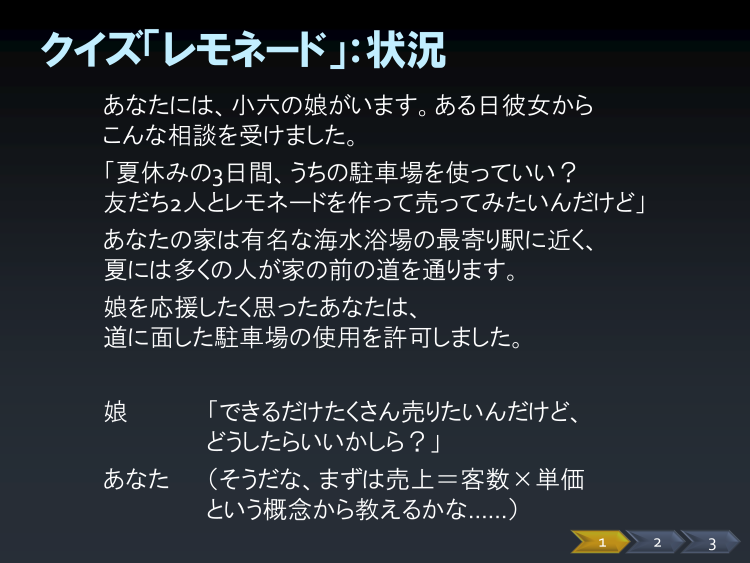
弊社が考える意志決定の枠組みである知・情・意の情の部分を学びたく門をたたき、いろいろ教えていただきました。
EQにお詳しい方々なので、「IQでパワーアップ」と称して論理的思考や問題解決のトピックをいくつか提供しました。
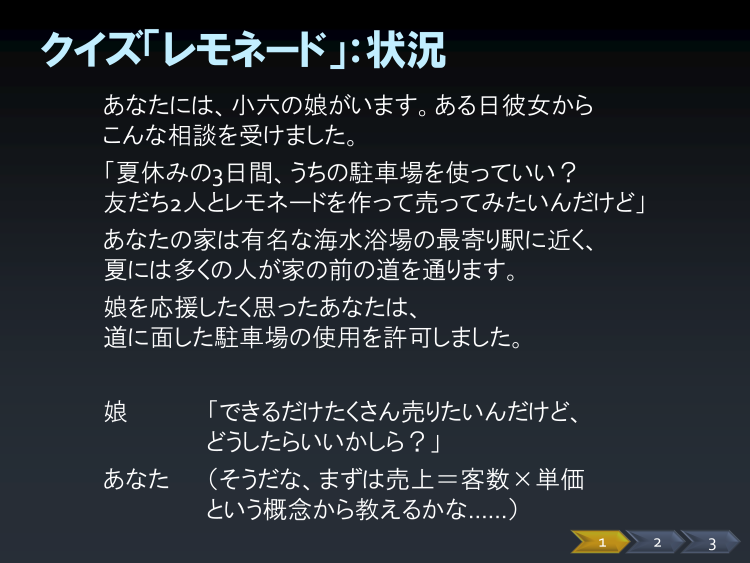
EQ関連サービスを提供している企業の皆様に、たくさん勉強させていただいたお礼に1日研修をプレゼントしました。
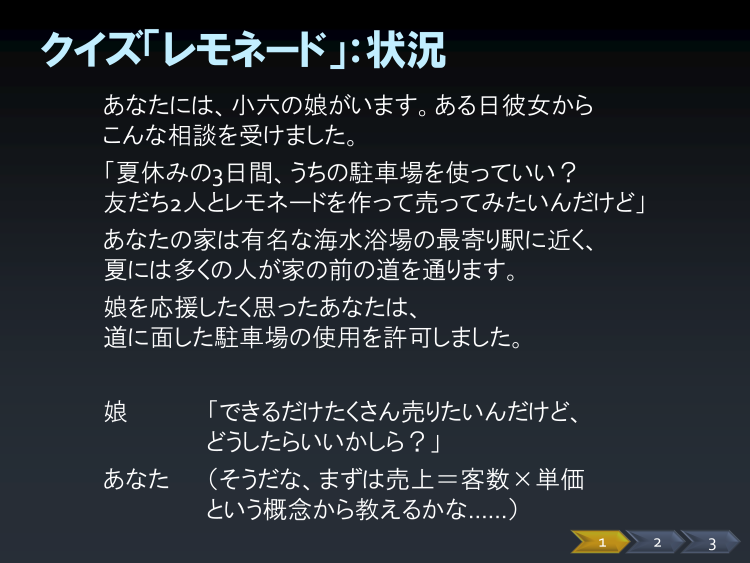
弊社が考える意志決定の枠組みである知・情・意の情の部分を学びたく門をたたき、いろいろ教えていただきました。
EQにお詳しい方々なので、「IQでパワーアップ」と称して論理的思考や問題解決のトピックをいくつか提供しました。
心理カウンセラーの衛藤 信之氏は、「ハーフアンサー法」という問題解決のアプローチを提案しています。ベストアンサー(完璧な答え)ではなくハーフアンサー、つまり「完璧ではなくとも、解決できそうな魅力を持った答え」を考えて、試していこうということ。なんとなく和製英語っぽい響きですので、氏の造語かもしれません。それはともかく、「ハーフアンサー法」はこのようなプロセスとして定義されています(1)。
3.のブレーンストーミングは「上司と部下が協力して、問題解決のためのアイデアを出し合う」ステップとなっています。分析的な問題解決のプロセスではその前に「問題の定義→分析→原因追及」といった手続きがあってしかるべきですが、それらはすべて1.に押し込まれています。「ハーフアンサー法」は、そういったアプローチと比較すると、ずいぶん乱暴なやり方のようにも思えます。
しかし、こういったカジュアルなアプローチには、当事者の心理的なハードルを下げられるという大きなメリットがあります。マネジャーとしては、確度の高い打ち手が見つからないことよりも、部下がやる気を持って問題解決に取り組んでくれないことのほうが、大きな問題だと感じる場合もあるかもしれません。そんな場合には「ベストアンサーでなく、ハーフアンサーでいい」と宣言するだけで、部下はリラックスできそうです。
ユニークなネットサービスを連発している面白法人カヤックを率いる柳澤 大輔氏も、ブレーンストーミングによってとにかくアイデアを出してみようと提言しています(2)。
一つの理由は、いわゆる「量が質を生む」からなのですが、氏はもう一つの理由を重視しています。それは「仕事が楽しくなるから」。アイデア出しは、そのプロセス自体に「楽しい」という効用があり、それが組織における好循環の原動力になるといいます。
もちろん、分析的な問題解決のアプローチにも、こういったカジュアルさを持ち込む余地はあります。いきなり打ち手のアイデアではなく、問題分析の切り口をブレーンストーミングで出していってもいいわけです。
重要な意志決定の責任を引き受けることがマネジャーの仕事ではありますが、それを受けて実行するのは組織のメンバーです。意志決定のプロセスに部下を参加させるために、「敷居を下げる」工夫を施す余地は、まだまだ残されているのではないでしょうか。
(1) 衛藤 信之 『上司の心理学―部下の心をつかみ、能力を高める』(ダイヤモンド社、2000年)
(2) 柳澤 大輔 『アイデアは考えるな。』(日経BP社、2009年)
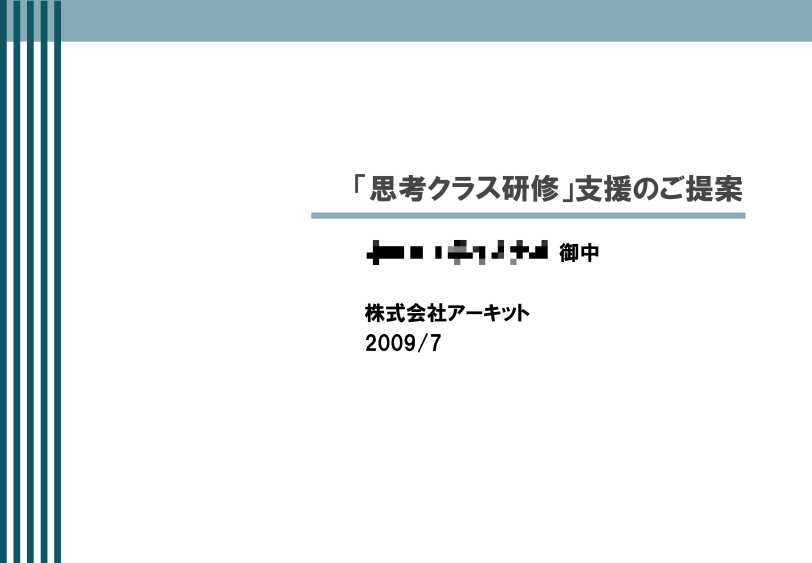
電機メーカーA社のある事業部門が、自部門内で思考力強化のための研修を設計・運用したいというご相談を受け、監修を担当しました。
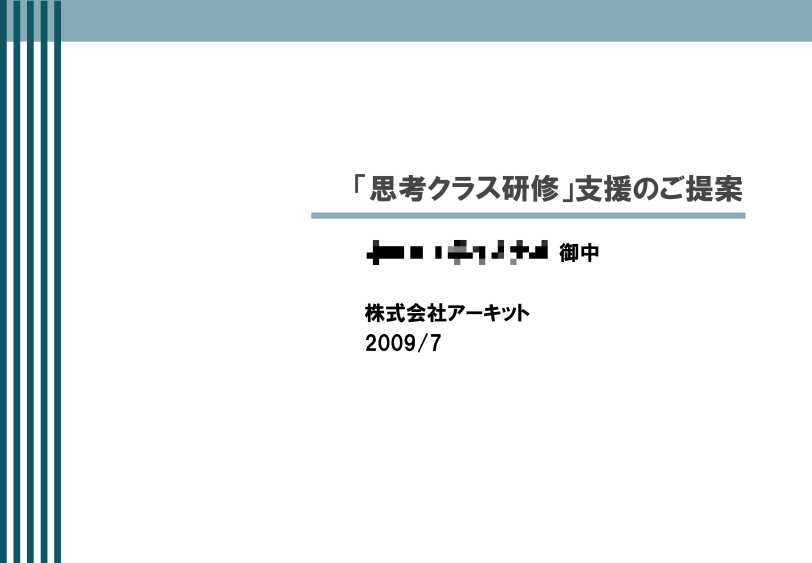
「考える」ことについて思い入れの深いお客様で、参加される皆さんにどんな演習を提供するか、考えること自体を考えてもらうためにどうするか、議論を重ねました。
弊社は成果物を作らず、お客様が作成した資料のレビュー、初回講義のオブザーブとフィードバックを実施しました。
ビジネスの世界では、よく「売り上げに責任を持つ」という言い方をします。これは、具体的には何を指しているのでしょうか。政治家や経営者が、不祥事の責任をとって辞任したりしますが、それと同じことなのでしょうか。もしあなたが部下から「責任を持つとはどういう意味ですか?」「責任を持って仕事をしているかどうかを、どう評価するのですか?」と聞かれたら、なんと答えますか?
「責任」をWikipediaで調べると、「義務あるいは義務に違反した罰を負担すること」とあります。すると「売り上げに責任を持つ」とは、売り上げ目標という義務を果たせなかったときに減給などの罰を負担すること……?それでは誰もすすんで責任を持ちたくなくなってしまいます。そんな会社もあるでしょうが、ここでは例外としておきましょう。
広辞苑によれば、「責任」には2つの意味があります。一部省略のうえ引用します。
(1) 人が引き受けてなすべき任務。
(2) 政治・道徳・法律などの観点から非難されるべき責(せめ)・科(とが)。
これを見ると、政治家や経営者の辞任は、主に(2)の意味での「責任」を取る行為であることが分かります。これに対して、われわれがある商品の「売り上げに責任を持つ」という場合には、(1)の意味合いが濃いでしょう。
とはいえ、(1)だけではすまないように思えます。実際、小学館の「デジタル大辞泉」では、両者の中間的な定義をもうけていました。
1 立場上当然負わなければならない任務や義務。
責任 とは – コトバンクより
2 自分のした事の結果について責めを負うこと。特に、失敗や損失による責めを負うこと。
3 法律上の不利益または制裁を負わされること。
われわれが仕事において「責任」という場合、程度の差はあれ、2の「結果について責めを負う」という意味合いを込めています。
しかし、単純なオペレーション業務などを別にすれば、ある結果が100パーセント個人の責任だといえるケースはそれほど多くありません。特定の期間の結果に影響を及ぼす因子は無数に存在します。そして多くは、その期間内の個人の力ではいかんともしがたいものです。たとえば売り上げでいえば、景気が悪くなった、製品に不具合があった、前任者が見込み顧客の開拓を怠っていた、などなど。
そもそも不確定な将来に向けて意志決定を重ねていくのですから、結果は分かりません。結果は不確実なのに、失敗すれば責めを負うことは確実だとすれば、合理的な個人はどう振る舞うか。なるべく失敗しないよう、保守的な仕事の定義をするでしょう。
それでは企業が成長できないということになれば、今度は成功に対して報酬が用意されるはずです。合理的な個人は、それこそディシジョン・ツリーでも作り、報酬が最大化されるような目標を立てるでしょう。
これは、要するにアメとムチです。責任を持つとは「結果が出たらごほうびを、出なかったら罰をもらう」というだけのことなのでしょうか。
それだけではないはずです。われわれが「責任感」を感じて何かをみずから引き受けるとき、そこには「イヤだけど義務だからやろう」という以上の、ポジティブな気持ちがはたらいています。その気持ちは、大辞泉の「1 立場上当然負わなければならない任務や義務」というイヤイヤ感のにじみ出た定義よりも、広辞苑の「(1)人が引き受けてなすべき任務」というすがすがしい言辞に、より正確に表現されていると感じます。
あなたがマネジャーとして、部下に「この商品の責任者をあなたにお願いしたい」というとき、そこに込めているのは「立場上の義務を負わせるぞ。うまくいけばごほうびをあげるが、失敗したら罰を食らわせるぞ」という気持ちだけではないでしょう。
「責任」の定義について一通り確認しましたので、冒頭の問いについて考えてみましょう。もし部下が「責任を持つとはどういう意味ですか?」「責任を持って仕事をしているかどうかを、どう評価するのですか?」と聞いてきたときに、どう答えるべきか。
一部は、上で見てきたような「結果責任を取ってもらう」という答えになるでしょう。しかし、それだけではないはずです。「結果に責任を取ってもらう」だけでは、「責任(感)を持って取り組んでもらう」という意味あいが伝わりません。
「ビジネスは結果がすべてなのだから、結果だけに責任を持つという考え方でよいではないか」という考え方もできます。しかし、これは効果的とは思えません。
まず、自分の能力が100パーセント、しかも即座に結果に反映される仕事でもない限り、仕事に投入した能力とその結果は一致しません。したがってわれわれは結果への評価に対して「報われない感」「不運感」を感じがちです。
とはいえ、長期にわたって評価を繰り返していけば、能力は結果として現れてくるものです。ですから、結果だけで判断するというやり方は、長期間のつきあいを前提とするならば、合理的です。
しかしそれでは、金の卵を腐らせてしまうリスクが高まります。逆説的なことに、長期間のコミットメントを引き出すためにこそ、能力を評価してあげることが重要なのです。そして、持てる能力をつねに十分に発揮してもらうためのキーワードが「責任」なのです。
以上をふまえて、わたしなりに定義をしてみます。責任を持つとは「(結果にかかわらず)最善を尽くすと約束する」ことです。結果が出ないときに工夫をすることはもちろん、結果が出てもそこで力をゆるめないということです。
評価との関係でいえば、仕事の責任を持つとは「この仕事に対する取り組みを、自分のベストの能力を発揮した結果として評価してもらってかまわない」という宣言です。マネジャーからすると「その仕事ぶりをあなたのベストとみなして能力を測りますよ」という宣言です。
今期はなんとなく調子が出なかったとか、求められる結果は出したので後半は流したとか、実際にはいろいろあります。「今期の仕事ぶりだけを見て能力を測られてはたまらない」と思うこともあります。しかし、仕事に責任を持つ、つまり「その仕事に最善を尽くす」と約束したのですから、「もっとできたのに……」「潜在的な能力も評価してほしい……」という言い訳はなしです。
部下に、ある仕事についての責任を持たせる、つまり「任せる」ときのポイントは何でしょうか。このコラムのテーマである意志決定に関わることでいえば、仕事の責任を、その仕事に関する決断の自由とセットにして渡すことではないでしょうか。
部下に特定の商品の売り上げを見させるならば、その目標を達成するための手段を決めるのは、その部下本人であるべきです。売り方や経営資源の使い方についてしばりをかけておいて、責任を取れというのは理不尽です。逆に、部下が責任を取れないことがらについて決断を強いるべきでもありません。
決める人が、決めたことに対して責任を取る。われわれは、生活のレベルでは否応なくこの原則を受け入れています。仕事でも、ときに難しい局面はあるとしても、「決める=責任を取る」の原則に立ち戻ることが、マネジャーとして部下の仕事にどこまで介入すべきかのガイドラインになると思います。
責任が「結果についての賞罰」と「最善を尽くすという約束」の二つの意味合いを含むとして、評価に当たってどのようにバランスされるべきでしょうか。主要な変数をいくつか考えてみました。
いま、10億円をかけて商品Aを開発するか、1億円で商品Bを開発するか、どちらかの選択があるとします。
決め手は、商品を投入できる2年後から3年間の景気動向。商品Aは生活への密着度は低いが遊び心にあふれているので、景気が上向き続ければ100億円の売上(3年間の累計。以下同様)を見込めます。しかし横ばいないし下降基調にあっては5億円しか期待できません。商品Bは逆に不況に強いタイプで、2億円は堅いと予測されています。ただし景気が上向いた場合でも、売上は5億円にとどまる見込みです。予測によれば、当該期間に景気が上向き続ける確率は5%でした。
こんな状況下で使えるのが、ディシジョン・ツリーです。この場合、商品AかBを選択し、それぞれのケースで景気が上向き続けた場合とそうでない場合があるので、4つのシナリオがあります。それぞれのシナリオの結果と、そのシナリオが実現する確率を掛け合わせ、商品ごとに足し合わせれば、商品ごとの結果(今回は売上)の期待値が計算できます。
そこから開発コストを引くと、商品Bの方が期待利益が大きいことが分かります。商品Aは赤字でした(流通・販売コストなどは一切無視しています)。
-0.25 億円 ┌好景気( 5%) ─100 億円
┌商品A(10億円) ─○
│ └不景気(95%) ─5 億円
□ ∧
│ ┌好景気( 5%) ─5 億円
└商品B( 1億円) ─○
1.15億円 └不景気(95%) ─2 億円 ツリーを広げたり、深めたりすることで、より精緻なシナリオが作れます。「広げる」とは、たとえば商品AとBに加えて「C」、好景気/不景気に「変わらない」という新しい選択肢を加えることです。「深める」とは、たとえば(3年後でなく)1.5年後の景気によって、次の1.5年の決断(拡大/縮小/撤退)をするといったことです。
ディシジョン・ツリーを作るだけでマネジャーの仕事が務まるならばよいのですが、残念ながらそうはいきません。マネジャーが実際に知恵を絞るべきは、ツリーにどの変数を採用するか、それぞれの変数にどのような値を与えるかといったことでしょう。おそらくは次のような問いを発しながら考えるものと思います。
「そもそも、われわれが変えられるもの、変えられないものは何か?」
「変えられないもののうち、結果にもっとも大きな影響を及ぼす変数は何か?」(景気)
「その変数はどういう状態を取るか?それぞれの状態になる確率は?」(景気予測)
「最終的な結果をどう予測するか?」(売上予測)
しかしどこまでいっても、ディシジョン・ツリーがマネジャーの代わりに決断してくれることはありません(一部の業務では実際に使われているそうです。ただし、ある程度定型化した業務か、長い経験から来る蓄積があるか、他に頼るものがまったくないかといったケースに限られるでしょう)。上の例のようなもっともシンプルなケースでさえ、商品Aの不景気時の売上予測を1.5億円だけ、あるいは好景気の見通しを2%だけ高めれば、結論は商品Aのほうに傾いてしまいます。
となると、いくら定量的に判断しようと思っても、客観的なデータが何もない中では、結局数字の遊びにしかならないのでしょうか。
かならずしもそうではないと思います。
ディシジョン・ツリーのようなツールを作る作業は、主要な変数に絞り込んだ上で網羅的に考えさせてくれるので、考えの抜け漏れを減らしてくれます。偏りがちな数値感覚も補正してくれます。たとえば今回のように、最終的な結果のリターンは大きくてもそれが生じる確率が低い場合にどれくらいが期待できるのか、われわれの直感はうまく働きません。
また、決断にいたるプロセスを改善してくれます。上の商品Aでいえば、5%しかない環境要因に依存するのはやはり危険ですから、たとえば中間のチェックポイントを置いて決断を多段階にする余地があります。
さらに、決断の過程が分かるので、後から振り返ったときの反省材料になります。抱いていた過大な期待や、見逃していた重要な変数に気がつくことができます。
この本のなかに、本コラムのテーマ「マネジャーの意志決定」に関わる文章があります。
意志という言葉は非常によく聞こえるけれども、何ごとについても明白な意志を発表する者は、神経質かあるいは小心な厄介者である。毎日三度食べるご飯でさえ、硬い軟らかいがある。この世を渡るとき、ご飯の炊き方についてあまりにも明白な意志を持っている者は、おそらく生涯の三分の二は、食事のために不満足を唱えて暮らさなければならないだろう。
「世の中に譲っても差し支えないことが多いものだ」という見出しの下にある文章です。
たしかに、マネジャーが袖をまくって現場に介入しなくても、そしてそのせいでベストな結果が出なかったとしても、実はあまり問題がないということはありますね。
仕事に直接介入しないまでも、マイクロマネジメント(部下の行動を必要以上に細かく管理すること)が好きなマネジャーもいます。よい悪いの基準をはっきり持つことは悪いことではありません。しかし、それが些事にまで及び、部下の行動をもその基準で評価するようになると、部下がみずから判断して行動する機会を奪ってしまいます。
問題は、それを快適に感じる部下もいることです。日常生活で ご飯の炊き方に明白な意志を持ち、それを表明し続ければ、周囲から疎んじられること必定です。しかし、自分で考えるのが面倒な部下は、細かいところまで上司に方向指示をしてもらい、Do-er(仕事を「する」だけの人)に徹するほうが楽と思うかもしれません。それが好ましくないのであれば、マネジャーはわざと意志を表明しないなどして、積極的に譲っていかなければなりません。
もちろん、なんでもかんでも譲ろうということではありません。続く見出しは「譲れないところは、あくまで固守せよ」。一転して、断固として譲るべきでない局面について述べています。
マネジャーとして何を譲らないか、一度時間をかけてリストを作ってみてはどうでしょうか。「それ以外は譲ってもいい」というリストを持つことで気が楽になりますし、決断も早くなると思います。
そのリストは、使いながら鍛えられていくものです。たとえば「部の目標を守る」ことだけは譲らないが、ほかのこと(各人のワークスタイルや経費精算のポリシーなど)にはあえて無頓着でいようと決めると、楽になることが多いと思います。しかし、「譲れない一線」のリストは一行ではないでしょう。たとえば二行目に「部下のメンタルヘルスを健全に保つ」とあった場合、一行目と矛盾が生じ得ます。
目標を達成しようと思うと、部下には休日出勤を含めてかなりがんばってもらわないとならないようなケースでは、譲れないはずの一線を譲らざるを得ないかもしれません。あるいは「どちらも譲らない」と考え抜くことで、第三の解(たとえば、他部署からの増援を頼む)を思いつくかもしれません。そういった経験をへて、リストが真に自分の判断基準になっていくのだと思います。
9.11テロは予測できた。なぜなら不審な動きは察知されていたから。先週の株価の上昇は、景気復活の予測が出た時点で予測可能だった。
「事前に知っていた情報があったのだから、あの出来事は予測できたはずだ」
行動経済学の研究によれば、われわれはそう思い込んでしまう傾向(後知恵のバイアス)があるそうです。イタリアで経済学を教えているマッテオ・モッテルリーニは、このように解説しています(1)。
私たちには、過去の出来事に意味を与え、それは以前の状況から避けようもなく生まれた結果なのだと考えるという、特殊な能力がある。そのために、前もって知っている情報があったのだから、すでに起こった出来事も予測できたはずだと、まちがって思いこんだりする。
つまりわれわれは、ある結果を自分の知っている原因に結びつけて「説明をつける」ことを好む傾向を持っているのでしょう。
われわれは、自分が知っている(数少ない)原因から強引に結果を説明してしまいがちである。つまり、あるチャレンジが成功したのは「自分のやり方がよかったから」で、失敗したのは「自分のやり方がまずかったから」だ、と実際以上に思いがちだということです。
もしそうならば、結果を振り返って反省する、あるいは経験から学ぶアプローチには、自分の意志決定のロジックを歪めるリスクがあることになります。結果が良かったからといって正しく決められたことにはならないし、結果が悪かったからといって決め方が間違っていたわけでもないのです。ふたたびモッテルリーニ氏の言葉を引用します(1)。
ある決定が正しいかどうかを知るには、その決定にともなう結果を考えるのではなくて、決定のプロセスを考えなければならない。「結果はどうでもいい」と言っているのではない。結果は大事である。けれども結果にばかり気をとられると、決定する前に直面していたリスクや不安定な状況を見過ごしてしまいがちなのだ。問題は、結果がわかった後で(事前に正確に予測することなど不可能だ)ある決定を評価するという方法が、将来何かを決定するときのやり方に影響を与え、よくない結果を出してしまうことである。
ではどうすれば、この「後知恵のバイアス」を取り除けるのか。わたしなりに考えたことをリストしてみます。
(1) マッテオ・モッテルリーニ 『経済は感情で動く―― はじめての行動経済学』(紀伊國屋書店、2008年)
『選ばれるプロフェッショナル』(1)は、顧客に何らかのアドバイスを提供するすべての職業人にとって有益な本です。もしあなたが顧客対面業務のないマネジャーだったとしても、あなたがサービスを提供している社内の相手や、あるいは部下を顧客に見立てれば、得られるものは多いでしょう。
この本では優れたアドバイザーが持つ資質を7つ挙げていて、そのひとつが「判断力」です。著者らは、よりよい判断を下すためのテクニックをこのようにまとめていました。
- 問題の理解に時間を惜しまない
- 本当の問題が何かを見つける
- その問題を本当に優先すべきかを確認する
- 「反証的」な質問をする
- 一般的な選択肢だけでなく異色の選択肢も考える
- 予想される未来から逆算する
- リスクや不透明性に対してクライアントの許容度を理解する
- 自身の経験を活かす能力を高める(経験豊富な同僚から学ぶ)
よりよい判断を下すための8つのテクニック – *ListFreak
ここでピックアップしたいのは「予想される未来から逆算する」という項目です。この部分についての解説を同書から引用します(1)。
予想される未来から逆算する……将来に関する状態について、次の二つの質問を比べてみよう。
○我々の一番の競合が、この先二年のうちに我々の市場シェアを一〇ポイント奪い、売上で我々を抜く可能性はどれくらいあるだろうか。そうなるとしたら、どのような理由が考えられるか。
次は同じ質問を多少変えたものだ。
○今から二年後を想定しよう。我々の一番の競合が市場シェアを一〇ポイント増やし、我々の売上を抜いている。どうしてそうなったのか、その経緯と理由を説明せよ。
二つ目の質問のように、仮説に基づいた事象を実際に起こったかのように提示されると、どうしてそうなったかについて、人はかなり独創的な理由を考えつく。そして思考の質は驚くほど高まる。
情報の具体性はまったく同じなのに、読み比べてみると、頭の働き方が違うことが実感できます。問う視点の置き方の重要性をはっきりと示す、よい例です。
将来から振り返ってみる発想は、目新しいものではありません。天気予報のように現状の延長線上に未来を描く”forcast”と対比させる意味で”backcast”と呼ばれることもあります。拙著『クリエイティブ・チョイス』(2)では、「マーリンメソッド」という名前で紹介しました。この方法では、まず目標を達成できた将来を思い描き、そこにいたる道のりを振り返ります。次の問いかけは『会社を変える 不合理のマネジメント』(3)から引用したものです。
- この戦略を実施するにあたり、どのような能力が必要だったか?
- あなたの会社はそのような能力をどこで身につけたか?
- 目標を達成した今、自分の会社をどう思うか?
- 目標を達成した今、自分の置かれた市場をどう見るか?
- この目標達成は何への出発点となるか?
- ほんとうに目標を達成したかどうか、どうやって判断できるか?
マーリンメソッド(未来から問いかける計画法) – *ListFreak
自分でもこのような方法論を紹介しておきながら、『選ばれるプロフェッショナル』の例題にはハッとさせられるものがありました。問いかけが対比されていたことで、発想の違いがよく実感できたということでしょう。
(1) ジャグディシュ・N・シース (著), アンドリュー・ソーベル (著), 羽物 俊樹 (翻訳) 『選ばれるプロフェッショナル ― クライアントが本当に求めていること』(英治出版, 2009年)
(2) 堀内 浩二 (著) 『必ず最善の答えが見つかる クリエイティブ・チョイス』(日本実業出版社, 2009年)
(3) ポール・レンバーグ (著), 山崎 康司 (翻訳) 『会社を変える 不合理のマネジメント―1.5流から超一流への発想転換』(ダイヤモンド社, 2008年)
先延ばし癖の矯正について述べた文章のなかに、「プレマックの原理」という言葉を見かけました。
「プレマックの原理」は、心理学者デビッド・プレマックによって公式化され、こう述べられています。「高い頻度で起こる行動は、低い頻度の行動を強化することができる」。(1)
引用した部分のすぐ後に、わかりやすい例が添えられています。
コーヒーを一杯入れることは、あなたがよくすることだし、苦でもないとします。一方で部屋の掃除は、めったにしないし、あなたにとっては難しいことだとします。このとき「プレマックの原理」にしたがえば、「部屋の掃除の後でコーヒーを入れる」というルールを作ることで、掃除の頻度を高めることができます。Wikipedia(英語版)では、実生活でもっともよく使われるこの原理の応用は「アイスを食べる前にお野菜をぜんぶ食べなさい」である、としています。
なぜ、「好きなことをご褒美にすれば、嫌なことでも習慣づけられる」というような表現ではないのか?他の情報源をあたってみたところ(2)、プレマックの実験がサルを使ったものであることに起因しているようです。プレマックは、実験室にボタンやレバーを並べておき、サルが自発的に起こす行動の頻度を測りました。その後、あまりしなかった行動(例:レバーを引く)をしないと、よく起こす行動(例:ボタンを押す)ができないように仕組んで再度測ってみると、前者の行動頻度が高まったそうです。サルに行動の好き嫌いを尋ねるわけにはいかないので、頻度の高い低いという表現になったのではないでしょうか。
実験は自発的な行動を測ったそうですので、「高頻度の行動 = 好きな行動」と置き換えてもよさそうです。しかし「低い頻度の行動 = 嫌いな行動」ではないでしょう。嫌いな行動は、そもそもしないでしょうからね。とすると「好きなことをご褒美にすれば、嫌なことでも習慣づけられる」は解釈しすぎということになります。
また、自発的な行動が対象であったということは、高い頻度で起こる行動なら何でも使えるというわけでもありません。「毎朝、イヤイヤだけど通勤するから、その前に運動しよう」というプランでは、プレマックの原理は働かないということです。これらを踏まえると、プレマックの原理を確実に理解するためには「行動」という言葉の前に(自発的な)を付けて、次のように理解しておけばよさそうです。
「高い頻度で起こる(自発的な)行動は、低い頻度の(自発的な)行動を強化することができる」
これらの知見を踏まえ、この原理を意志決定の質を高めるためにどう使えるかを考えてみました。
われわれは、つい「決め急ぎ」「決め打ち」をしてしまいます。後から振り返ってみれば「ちょっと気を配っておけば……」というところに気が回らず、偏った決め方をしてしまうことがあります。
そこで、こんな感じで自分を「しつけて」みてはどうでしょうか。
などなど。しばらくメモを続けていると、「こういうことも考えておけばよかった」という後悔の数だけ、決め方のバリエーションも出てくると思います。
われわれの日常は選択の連続です。ランチの決め方など小さい選択にも、われわれの癖は表れます。試す機会はたくさんあります。
(1) マイケル・R. エデルシュタイン ほか『論理療法による3分間セラピー 考え方しだいで、悩みが消える』
(2) たとえば「プレマックの原理」 – カウンセリングオフィスクローバーリーフ・臨床心理士のブログ。
部下のAが相談に来ました。マネジャーのあなたはこう答えます。
「ごめん、いま時間がないんだ。明日のプレゼンの準備をしなくちゃならないんだよ。明後日でいいかな?」
しかしプレゼン当日、顧客からの追加オーダーを受けてしまいます。
「ごめん、明日までって言われちゃってさ。ちょっと延ばしてもらってもいいかな?」
そんなこんなで数週間がすぎたある日、Aが「突然」辞めたいと言い出します。
間が悪いことに、その日は特に動かせないアポが続けざまに入っています。
「どうして突然そんなこと言うんだ!明日の朝イチに時間取るから、詳しく話を聞かせてよ」
こういうケースを「後から」「他人事として」ながめると、問題はあきらかですよね。それは「突然」起きたことではないのです。緊急事項に追いまくられて、重要事項をおろそかにしてしまったということです。Aさんが抱えていた問題は、「辞職」という段階にまで悪化して、ようやく問題として認識され、あなたの「緊急事項」リストに載りました。
しかし、こういうケースに「現場で」「わがこととして」遭遇した場合、どうすればよいのでしょうか。個々の局面での判断を見ていくと、「無理もない」と思えてしまいます。部下の相談にはいつでも乗れますが、顧客へのプレゼンは期日が決まっています。
もちろん、相談の内容にもよります。仮にAさんが「死にたい」と言ってきたら、プレゼン準備をあきらめる、プレゼンの日をずらしてもらう、いっそプレゼンをあきらめるというような選択をするでしょう。しかし、それはAさんの問題の「緊急度」が高まったからにすぎません。
ここで考えたい問題の本質は、常に緊急対応を続けるような状態から、いかに脱するか?ということです。
時間管理の方法論は、これにも答えを用意しています。「緊急事項」は即座に対応しなければならないから「緊急事項」なのですから、起きてしまえば対処せざるを得ません。そこで、より予防的なアプローチを考えます。そもそも「緊急事項」を減らすことはできないかと考えるわけです。
やるべきことを緊急度と重要度の2軸で色分けし、緊急度にかかわらず重要度の高いことにフォーカスをしていく。そうすることで、将来「緊急事項」として浮上するかもしれない問題にも、潜在化している段階で手を打つことができます。その結果、後手後手だった仕事のスタイルが徐々に改善されていくという理屈です。
こういった方法論を本で読んだり研修で学ばれた方は少なくないでしょう。わたしも、その一人です。いろいろと実践を試みてきました。もっとも難しいポイントは「重要度の高いことの重要性を自分に認識させる」ことだと思います。
たとえば「部下が最高のパフォーマンスを発揮できている状態を保つ」ことに【重要】とラベルを貼ったとしましょう。しかし、もし「顧客の期待を超える」ことも【重要】だったとしたら、これらはしばしば両立しません。冒頭のケースはまさにそういう状態です。まずは両立させるようなアイディアを探るべきでしょうが、それでもダメだったら、より重要な(あるいは緊急な)ほうを選ばざるを得ません。
このとき「重要な問題の一つに手を打たなかった」事実を自分に強く認識させられなければ、また同じ過ちを犯してしまいます。重要と思っていたのに放置した問題が、ある日「突然」の緊急事項として浮上してきます。【重要】とラベルを貼ったものに手を打てないまま、かなり長い時間を過ごしてしまったわたしとしては、ここが一番の難所だと思っています。
そこで、わたしがときどき試みている方法を紹介します。それは「能動態に言い換える」こと。いま一度、冒頭のマネジャーの発言を振り返ってみます。
「ごめん、いま時間がないんだ。明日のプレゼンの準備をしなくちゃならないんだよ。明後日でいいかな?」
相談に乗りたいが、プレゼン準備のせいでそれができない、申し訳ないという気持ちが表れていますね。これを能動態に言い換えるとは、自分の行動(プレゼン準備)を自分の主体的な選択であると宣言するということです。たとえばこんな感じです。
「ごめん、今日は明日のプレゼンの準備を最優先にしたいんだ。明後日でいいかな?」
たったこれだけですが、自分の重要度をはっきりさせる(そして、それを伝える)ことからくる心理的な抵抗は、ことのほか大きいものです。実際、こんなふうに言おうと思った瞬間、
「部下は『自分が大事に扱われていない』と思って気を悪くするんじゃないか?」
と、ためらいを感じます。しかし実際に行動を見れば、そのとおりなのです。部下の相談に乗るよりも、目の前の仕事のほうが重要という選択をしたのです。それを自分に思い知らしめるために、能動態で言ってみるのです。
わたしが感じる最も大きな葛藤は、しばしば家の中で起きます。家で仕事をしているところに子どもがやってきて、遊ぼうと言ってくるときです。そういうときには
「ごめん、いま時間がないんだ」でもなく、
「ごめん、これを明日までにお客さんに出さなきゃいけないんだ」でもなく、
「ごめん、この仕事をやりたいんだ」と答えるようにしています。
このように能動態で表現すると、いつも選択の痛みを味わいます。なぜそれを重要と考えているのか。それなのになぜ、それにふさわしい時間を割かないのか。そういったことを自分に考えさせてくれます。
もしほんとうに子どもと遊ぶことが重要であれば、お客さまにご迷惑をかけることを覚悟して、いわば職を賭して、遊ぶことだってできる。しかし、そうはしたくない。それよりは、子どもの不興を買ってでも、今日は仕事を選びたい。それが社会で果たしたい役目でもあるし、そうすることで、長期的には多くの時間を子どもと過ごせることにもなるのだ。それに、「仕事をしなければならないので遊べない」と言えば、子どもは「父は誰かに仕事をやらされている」と思うだろう。それは本意ではない……といった思いが、頭の中を駆けめぐります。
わたしの場合、このような葛藤を経て、【重要】とラベルしたことの重要性が、自分の中に浸透していきました。どうも後手後手モードが直らない人は、お試しになられてはいかがでしょうか。
※ 能動態で表現するときには、ふだん以上に相手への配慮が欠かせません。特に、結果的にお断りをするようなときには、相手の気分を害さない配慮が求められます。自分のなかでの重要度をはっきり伝えられるかどうかは、お互いの人間関係によるところもあります。ここで書きたかったのは、何がなんでも口に出して言い切ろうということではなく、「選択を、他のなにかのせいにしないで主体的な行為としてとらえ直せば、『重要なこと』の重要性を腹に落として理解できる」ということです。