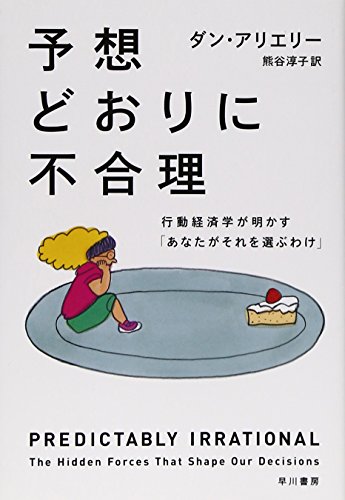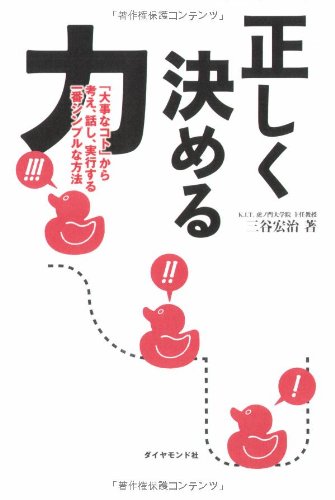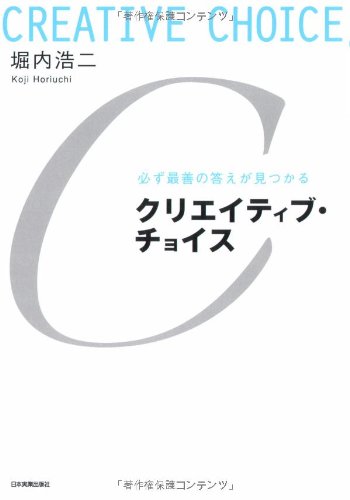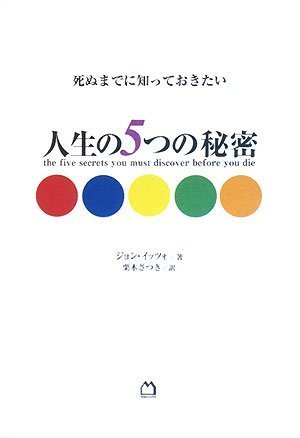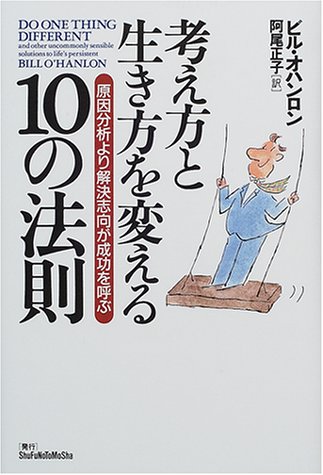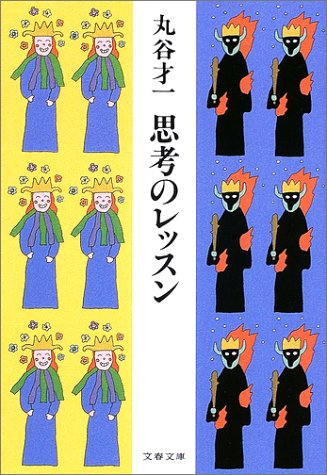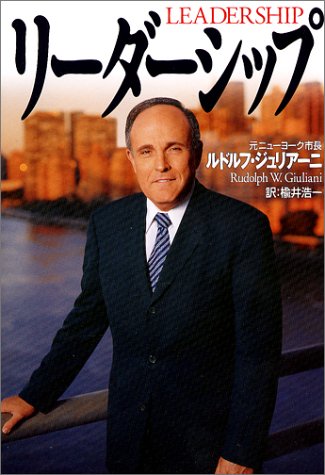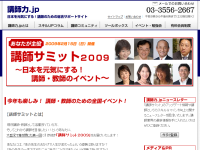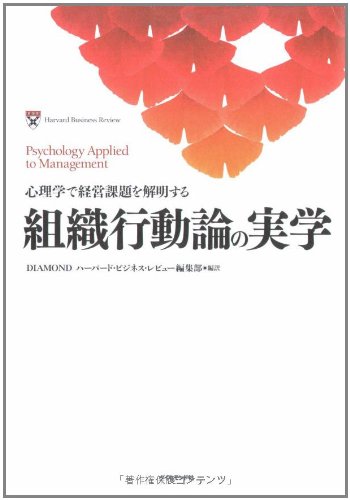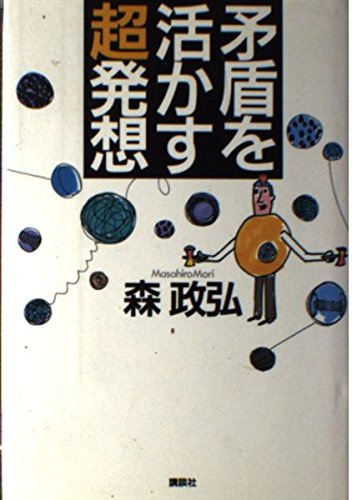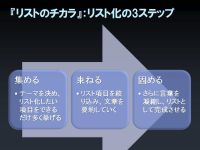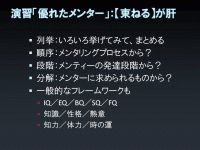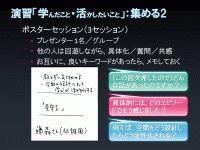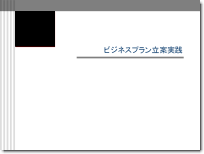● われわれは、比較しやすいものを好む
売上高が微減となる見込み――。こう聞いて、問題意識を感じないマネジャーはいないでしょう。われわれは、マイナスはダメ、プラスならとりあえずOKと考えるべく習慣づけられています。
しかし、プラスマイナスというのは、何かと比較して初めて言えることです。例えば、売上高の絶対額を前年度と比較すればマイナスだが、実は社員数が減っていて、1人あたりではプラスだった。あるいは、実は市場が冷え込んでいて、シェアは前年度比プラスだった。見方を変えれば符号が反転することはよくありますが、状況が変わるわけではありません。
行動経済学の研究者ダン・アリエリーによれば、われわれには「比べやすいものだけを一所懸命に比べて、比べにくいものは無視する傾向がある」(1) そうです。著者はそれを証明するためにユニークな実験をいろいろと考案しています。ここではそれらを翻案した架空の実験で説明してみます。
例えば、あなたは採用担当者だとします。有名大学卒業だが覇気のないA君と、学歴は高くないがガッツのありそうなB君の、二人の大学生どちらを採用するかで悩んでいます。総合的にはどちらも同じくらい魅力的だからです。
この二者択一が、「やや有名大学卒業だが覇気のないA’君」という候補者が加わったことによって、三者択一になりました。選択肢に何が加わろうと、A君対B君の相対的な評価は変わらないはずです。しかし、そうはなりません。われわれは断然A君の方を選んでしまうのだそうです。A君がA’君に比べて明らかに優位であるという認識が、A君対B君の相対的な評価をも動かしてしまうのです。
● 問題を「差」だけで捉えない
このメカニズムは、企業が差別化を図ろうと競争していって、結果的に均質になってしまう皮肉をよく説明しているのではないでしょうか。
「比べやすい違い」だけをピックアップして、それを互いに埋めようとしていけば、徐々にミクロな戦いになり、しまいには違いが無くなってしまうのは明らかです。そこで「他者が絶対に真似できない競争優位を持とう」という、これもよく聞く話になります。しかし、発想がすべて「差」から生じている限り、それは他社から見てもキャッチアップ可能な優位です。
では、どうすればよいのか。経営コンサルタントの三谷 宏治氏は、正しく決めるためのコツの一つとして、『大事なコトを「差」でなく「重さ」で決める』(2) と表現しています。大事なことは他社(他人)との「差」ではなく、自社(自分)にとっての「重さ」であると考える。
「重さ」も最終的には何かの「差」として、たとえば本来あるべき姿と現状との「差」として、表現する必要があるでしょう。しかし、測れそうな「差」を見つけて事足れりとしないことを心がけておくことで、冒頭で述べたような心理的な偏りを小さくできるのではないでしょうか。それが、問題の本質を把握・表現する力につながっていくのだと思います。
(1) ダン・アリエリー 著 『予想どおりに不合理―行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』 (熊谷 淳子 訳、早川書房、2008年)
(2) 三谷 宏治 著 『正しく決める力―「大事なコト」から考え、話し、実行する一番シンプルな方法』 (ダイヤモンド社、2009年)