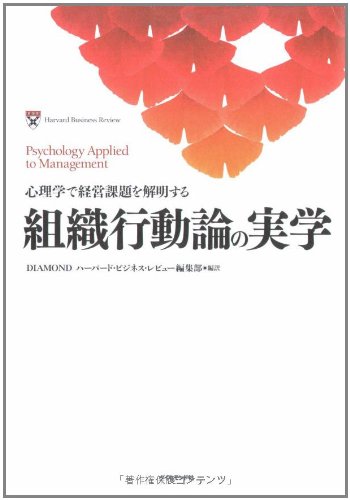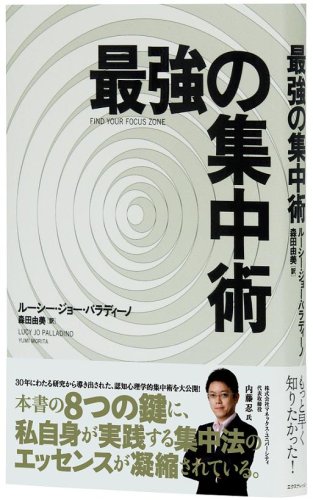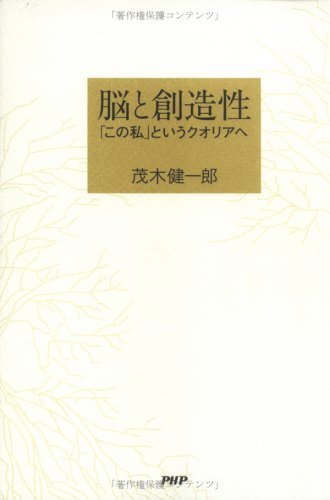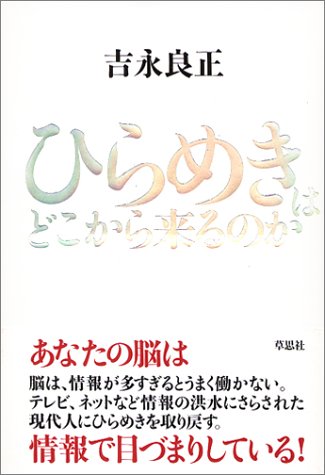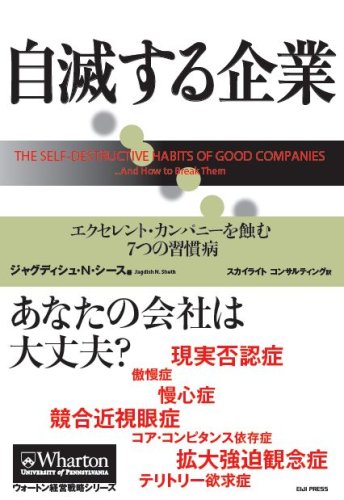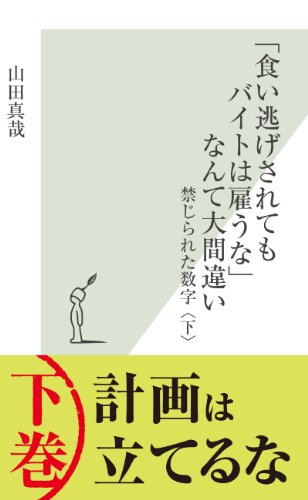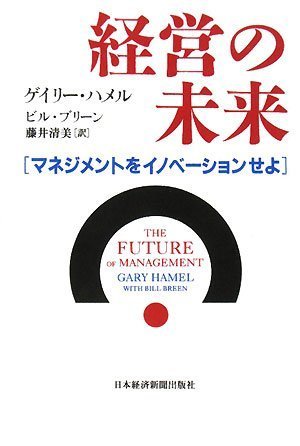●噂は悪者か、貴重なシグナルか
人間は自分の能力を高く評価しがちですが、経営者や起業家は特にその傾向が顕著だそうです。こう書いても、驚く人は少ないでしょう。ノーベル経済学賞受賞者でもあるプリンストン大学のダニエル・カーネマン教授らは『経営者はまた、自分が何もかもコントロールできるという錯覚を抱きがちである。実際、計画がうまくいった場合、その成果における運の部分をあからさまに否定する傾向がある(*1)』と述べています。つまり成果が出続ければ出続けるほど、「計画信者」になってしまうわけですね。
しかし、計画の過信による失敗が多いのも事実です。ミシガン大学ビジネススクールで組織行動学および組織心理学を教えるカール・ワイク教授は、計画についてこう言っています。『計画は、不測の事態をなおざりにしてしまうという落とし穴に我々を誘い込みます。その意味で、計画は噂の対極に位置するものです(*2)』
この、最後の一文にピンと来るものがありました。噂は、ああなりそうだこうなりそうだという不測の事態の候補をまき散らすという意味で、計画の対極に位置するものです。噂は、リスク要因を草の根レベルから掘り起こす可能性を秘めています。ワイク教授はこうも語っています。『どのような組織でも、最も影響力の大きいストーリーは噂を通じて生み出され、広まっていきます。実際、噂とストーリーテリングとの間に基本的な違いはないと思います(*3)』
たとえば、創業者がクレームを手がかりに大口顧客の信頼を獲得した話は「ストーリー」だが、確執のすえに共同創業者を追い出した話は「噂」。ストーリーと噂の違いは、それが経営者にとって都合がいいかどうかの違いなのかもしれません。
「噂なんかに任せず、悪い見通しであっても部下に率直に報告させればいいじゃないか」と思ったとしたら、それもまた「コントロール過信症候群」かもしれません。そのように率直にものを言ってくれる存在は貴重品と呼べるくらい少ないのが実際のところのようです。INSEADのマンフレッド・ケッツ・ド・ブリース教授は、その存在を「道化師」と呼んでいます。『いかなる組織においても、リーダーに遠慮会釈なく物を言い、本当の現実についてリーダーに告げることをいとわない存在が必要なのです。これはまさしく道化師の役割です(*4)』
●噂によるマネジメントの可能性
ここまでをまとめてみましょう。
- 経営者は自信過剰である
- 計画の過信は不測の事態をなおざりにしまう
- 噂は不測の事態を掘り起こしてくれるという意味で、計画の対極的な存在である
- 噂は組織がストーリーを共有する強力な手段である
- リーダーに率直に現実を告げられる人間(道化師)はまれである
これらを眺めていると「噂を道化師役にして、不測の事態に備える」ことはできないかというアイディアが浮かんできます。われわれは噂を好ましくないものと見なしがちです。噂はコントロールできないし、組織の結束力を弱めるリスクがあります。しかし噂を抑圧せず(抑圧すればするほど広まるのが噂なわけですが)、振り回されず、うまく付き合って意志決定の材料とすることはできないでしょうか。
ここで性急に「匿名の社内掲示板はどうだろうか」等と打ち手の話を始めてしまうと議論が小さくなってしまうので我慢しておきます(導入事例はあるようですね)が、覚えている事例を一つ紹介します(出所を失念してしまいました。わたしの実経験ではなく書籍で読みました)。
あるプロジェクトではマネジャーが噂を耳にするとそれを紙に書いて壁に貼りだしていたそうです。そのうえで、皆の関心の高そうな噂にはマネジャー自身の見解を書き入れていたとのこと。根も葉もない噂によるプロジェクトの動揺を食い止めつつ、マネジャーが見逃している「不測の事態」を見いだせるかもしれません。うまく機能すれば、ある種のコミュニケーションチャネルになるかもしれませんね。
(引用文献)
いずれも DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部 『組織行動論の実学―心理学で経営課題を解明する』(ダイヤモンド社 2007年)所収。今回は、この論文集で何か一本書いてみようという挑戦でした。 「噂によるマネジメント」の実現可能性については他にも考慮すべきポイントがたくさんあります。思考実験としてお読みいただければ幸いです。