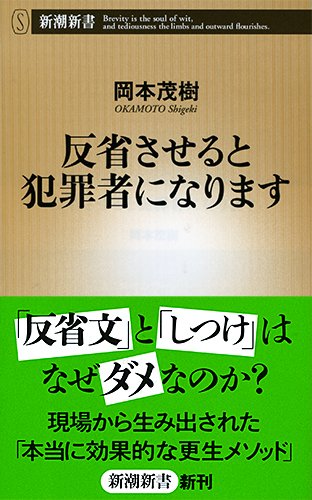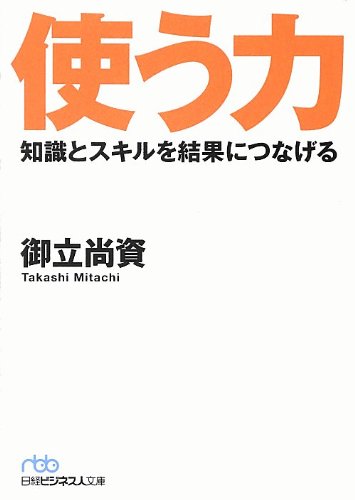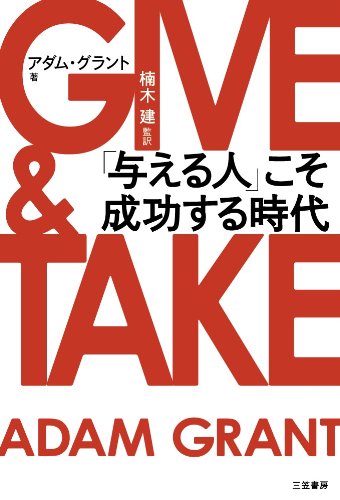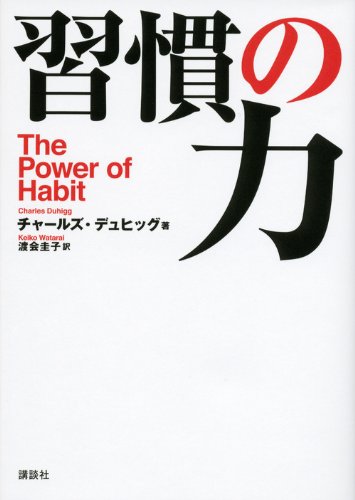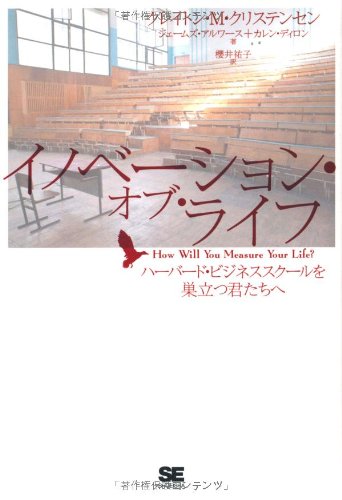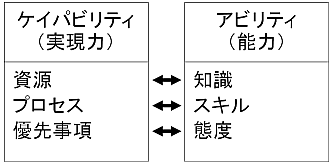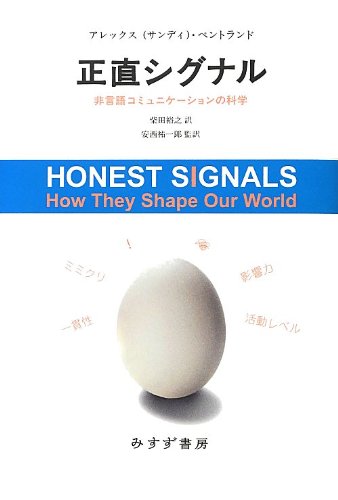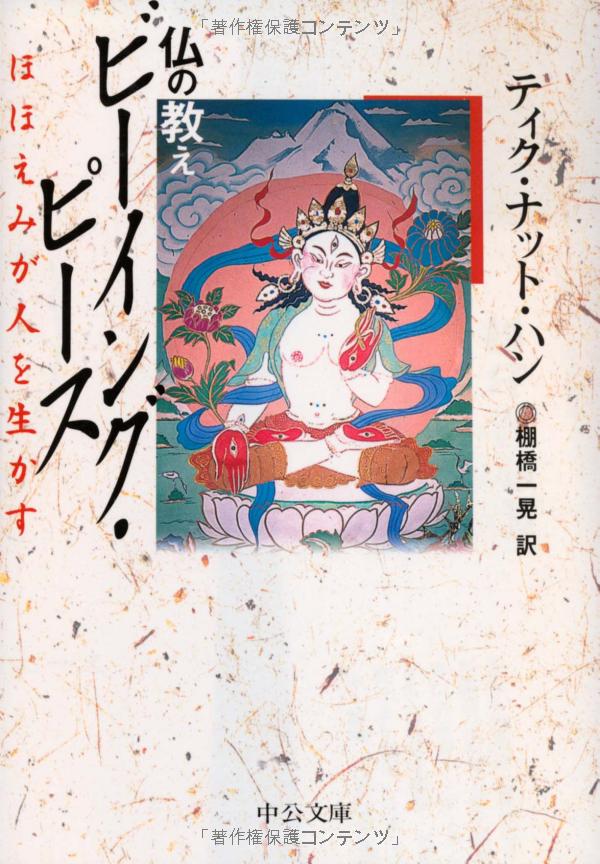【反省させると犯罪者になる】
罪を犯した人に対してすぐに反省させるだけでは、表面的な反省が上手になるばかりで、その人の更正にはつながらない。刑務所で受刑者の更生を支援している岡本茂樹氏は、ご自身の臨床経験に基づいた著書『反省させると犯罪者になります』でそう述べています。
一般的な社会人の文脈に置き換えれば『仕事の失敗を反省させるとローパフォーマーになります』という感じでしょうか。たしかに職場では「反省すればいいってものではないぞ」なんて小言が飛び交っています。そこで今回はよい反省と悪い反省について考えてみます。
【「失敗即反省」はあてにならない】
例えばAさんはセールスパーソンで、自分で立てた売上目標に到達しなかったとします。
もっとも効果がなさそうなのは、おそらく「もう二度と失敗しない」という「オウム返しの反省」です。決意は重要ですが、ここで考えを止めてしまっては反省とはいえません。次からどうするかと問われたら「がんばります」くらいのことしか言えないだろうからです。
次に効果がなさそう、というか怪しいのは、「自分勝手な原因の決めつけ」です。失敗を避けるためには失敗の原因を探らねばなりません。きちんと分析すれば、売れない原因は商品知識が足りないせいかもしれないし、価格が高いせいかもしれないし、商品そのものの魅力が小さいせいかもしれません。でもAさんにとっては商品知識をみっちり学び直すのは面倒だし、価格体系の見直しは大ごとです。そこでつい、恣意的に原因を採りあげてしまいます。
たとえば、自分が解決しやすそうな原因に帰属させてしまう場合。Aさんはトークが好きでかつ上手なだけに、どんな失敗も「言い方」ひとつで克服できると思ってしまいます。
あるいは、失敗の言い訳がしやすそうな原因に帰属させてしまう場合。Aさんはトークに苦手意識があって、どんな失敗も「言い方」のせいにしがちです。
どちらの場合も、結果としては「反省を踏まえて」プレゼンテーションの講座を受ける、といった改善案につながります。しかし本当の原因を解消する打ち手でなければ、効果は期待できません。
【失敗を再現する】
ではどうするか。岡本氏は、罪を犯した人に対していきなり「被害者の身になって考えろ」ではなく、まず加害者自身のことを考え(感じ)てもらうそうです。たとえば暴力事件であれば、加害者自身が暴力の被害者だったことが多く、暴力という形で発散させてきた自分の否定的感情に気づくのが、真の反省に向けての第一歩だということでした。結果として生じた犯罪でなく、まずは罪を犯すに至った自分を見つめるというプロセスにハッとさせられるものがありました。
犯罪と仕事の失敗を一緒くたにしては論じられませんが、「反省で重要なのは、失敗にいたる過程を再現すること」と捉えれば、生かせるアイディアのように思います。
失敗の再現という言葉から、囲碁の検討あるいは将棋の感想戦が連想されました。囲碁や将棋では、対局後に打ち手を再現しながら勝負の分かれ目を確認したり、ここでAでなくBと運んでいたらどうなったかというシミュレーションをしたりします。
検討や感想戦は、勝負のプロが失敗から学ぶために確立した方法ですから、失敗を(心の中で)再現するのも、反省への有効な道のはずです。
ファクトを追いながら、失敗をしたときの思考・感情・行動を再現する。何が悪手だったのか、なぜ悪手を打ってしまったのか、次はどうするかを考える。これは心理的にはタフな作業です。だからこそ前述の「自分勝手な原因の決めつけ」をしておしまいにしたくなるのでしょう。それこそ囲碁・将棋のように、くり返し挑戦可能なゲームとして捉えるのがよいかもしれません。
また検討・感想戦では相手の話を聞くことができます。自分がこう考えていた局面で相手がどう考えていたのかを知ることができるのは、失敗の原因を把握するうえで大きなメリットです。失注した顧客から本音を聞く機会はなかなかありません。ただ継続的な関係を築けている相手であれば、個々の提案は一局のようなものです。対局後の検討を申し込むことは可能でしょうし、相手はむしろ喜んでくれるのではないでしょうか。