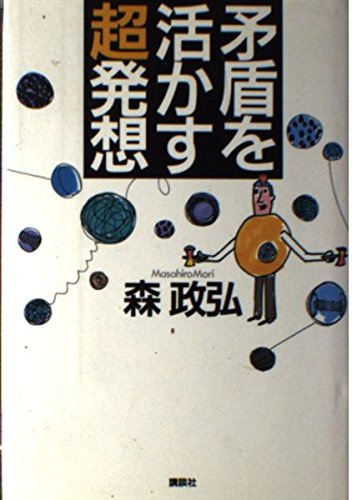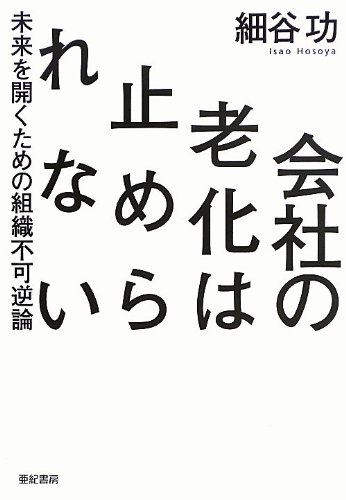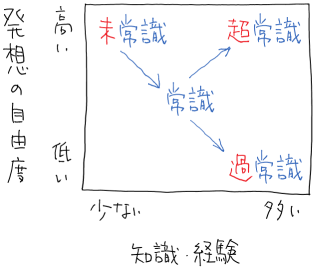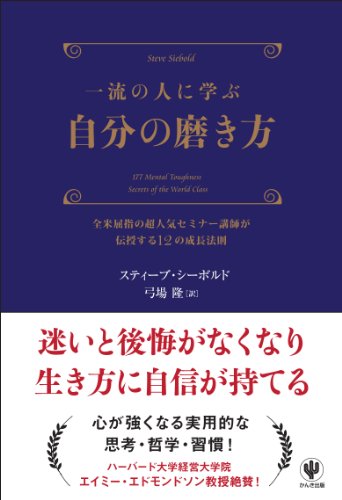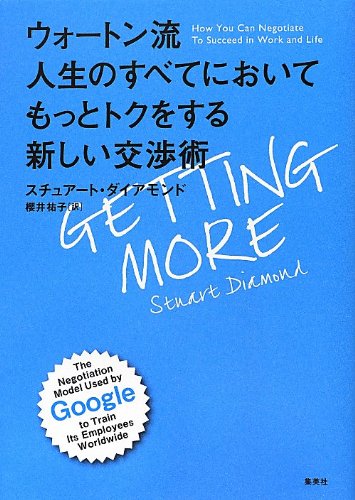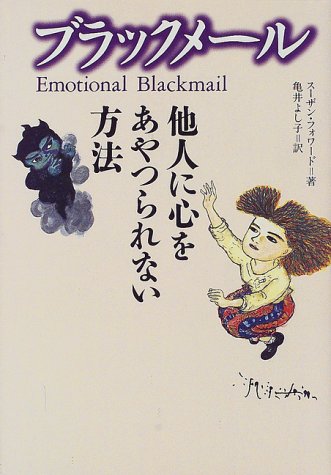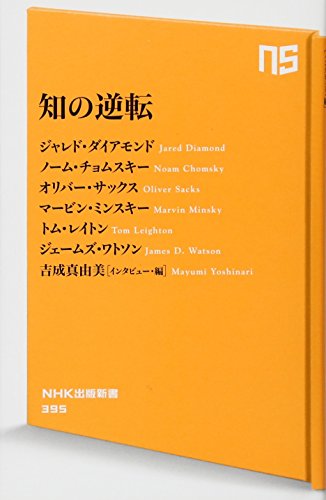●社長の選択
社長になったつもりで次のシーンを読み、何ができるかを考えてみてください。これは、ヘンリー・クラウド『リーダーの人間力』で紹介されていたエピソードを編集し、クイズに仕立てたものです。
《シーン1》 従業員満足度調査を実施したところ、福利厚生サービスに対する不満が明らかになった。しかし自社はかねてから従業員に最善のサービスを約束しており、事実、福利厚生サービスには同業他社よりもコストをかけている。どうするか?
- A1. 従業員に事実を説明し、現状に感謝し満足すべきだと訴える
- B1. その他「 」
A1も悪くない打ち手ですが、十分とはいえません。サービスの良し悪しは、会社がかけたコストではなく従業員のメリットによって測られるべきでしょう。ですからB1として「費用対効果の観点から同業他社と比較し、さらに良いサービスを探す」という選択が思いつけます。社長もそのようにしました。
《シーン2》 調べてみると、コストに見合ったメリットを提供できていないこと、市場にはもっと有利な条件の福利厚生サービスがあることがわかった。このサービスは内容が手厚いだけでなく、コストも低い。どうするか?
- A2. 新サービスの導入を発表し、自分が従業員の声に耳を傾けたこと、約束どおりに市場で最善のものを提供すること、会社のコスト削減にもつながることを説明する
- B2. その他「 」
A2は妥当な行動に思えます。従業員はもちろん喜ぶでしょう。妥当どころか、これ以上やるべきことはちょっと思いつけないという感じです。しかし、社長が選んだのはB2でした。何ができるか、先に進む前にすこし考えてみてください。
● いつも Win-Win が最善ではない
《シーン3》 社長は、浮いた資金を信託に回して従業員の退職手当を手厚くすることに充てようと考えた。
なるほど。A2には「一回の取引ごとにWin-Winを確定したい」という考えがあるように思えますが、B2(シーン3での社長の選択)はもっと長期的な視点に立っています。福利厚生サービスの不満が解消される上に、リクエストしてもしない手当がつくわけです。従業員の満足は労働意欲に反映され、めぐりめぐって会社に利益をもたらしてくれるでしょう。このように、今すぐの見返りを期待しない利他的な行動をお互いにし合う関係は、互恵的利他主義と呼ばれます。
もう1シーン、続きを読んでください(これは引用ではなくわたしが追加しています)。
《シーン4》 しかし、コンサルタントはこのように進言した。
「退職手当を増やすと従業員満足度が高まるというデータはない。金銭的な処遇は衛生要因、つまり『それが低いと不満を持つが、高くなるほど満足度が高まるわけではない』ので、従業員の満足度が大きく高まるとはいえない。そもそも、従業員が満足したから利益が向上するというのも、世間で言われているほど確かなものではない。コスト削減によって利益が得られたのなら、株主など短期的かつ金銭的なメリットに価値を置く他のステークホルダーに還元すべきだ」。どうするか?
つまり、見返りはないかもしれないよ、ということです。たとえば株主配当に回せば、株主の満足は確実に高まるわけですから、そちらのほうが会社にとってはよい選択かもしれません。
● 互恵はなくても信頼はある
想像ですが、この社長はそれでも従業員の退職手当を手厚くするほうを選ぶと思います。そう思える理由を説明するために、シーン3の選択にいたる部分を丸ごと引用します。
彼は考えた。「待てよ。会社としては福利厚生の予算はすでに取り分けてある。コストは計上済みであり、それを負担することには何の問題もない。そもそもこの資金は従業員に振り向けてあるものだ。今回、検討の結果、福利厚生費が当初予算より少なくて済むことになった。この際、浮いた資金は信託に回して従業員の退職手当を手厚くすることにあてよう。この資金はすでに従業員のために取り分けてあるものだ。浮いた分の恩恵は従業員に回そう」
源泉が商品の売り上げであれ福利厚生予算の圧縮であれ、利益は利益です。社長のようにお金に色をつけてしまうのは心の会計(メンタル・アカウンティング)といって合理的でない行為とされています。
しかしおそらく、そんなことは社長もご存じでしょう。それでも上記のように考えたとすれば、行為を選ぶ基準が「見返りがあるか、儲けを最大化できるか」ではなく「従業員への約束を果たせるか、信頼を示せるか」というところにあったのだと思います。
本書では『信頼し信頼されるということについて、人間性のあり方は三つに大別できる』とあります。
- 【被害妄想】相手を警戒し、報復の準備をしながら関係を保つ
- 【互恵取引】相手がくれるかぎり、こちらも与える
- 【真の信頼】ただ、相手に最上を望み、相手のために最善を尽くす
信頼関係の3つのあり方 – *ListFreak
相手のために最善を尽くすし、相手も自分のために最善を尽くしてくれると期待する。しかも見返りの有無とは関係なく、無条件に。
この最後の項目は、伴侶や親子の間柄であっても難しいと思います。雇用関係にある経営者と従業員の間でこのような信頼関係を築くのはさらに困難な挑戦です。業績のためにそこまでの信頼関係が必要かどうかもわかりません。経営者と従業員は【真の信頼】で結ばれるべきだとか、困難であってもそのレベルに挑戦しようとか、そう主張したいわけでもありません。
ただ、自分はA2で満足してしまいました。社長の行動を読んで驚きましたし、実行するしないは別にしても、そのような選択肢を創造できるようになりたいと感じました。そこでこのようにステップを踏んで社長の考えを追ってきました。そしてわかったことは、社長が「信頼」という状態に対するイメージをはっきり持っていたであろうこと、そのイメージから目をそらさずに考え続けたであろうということです。