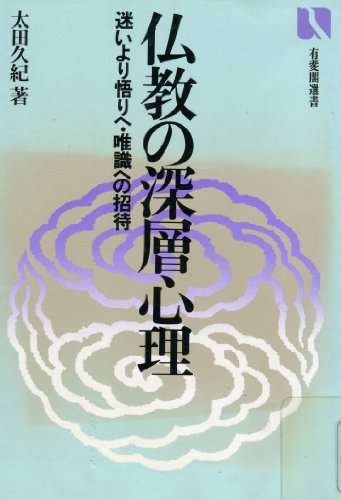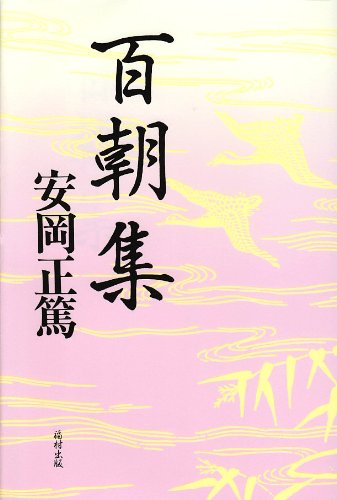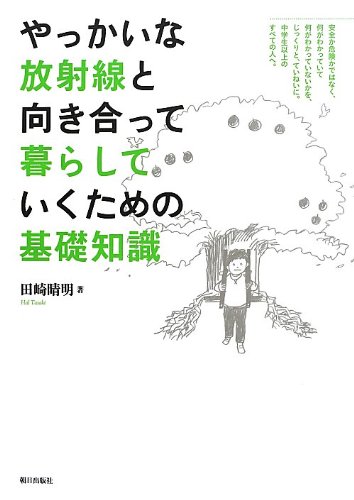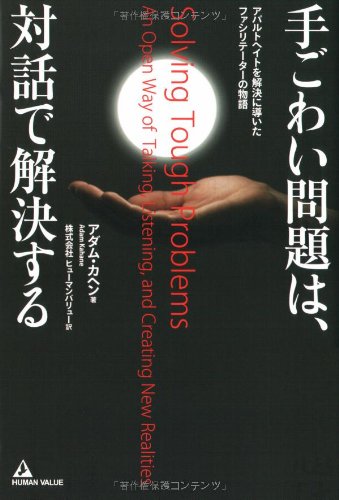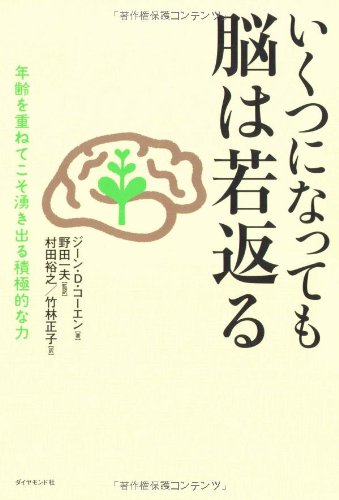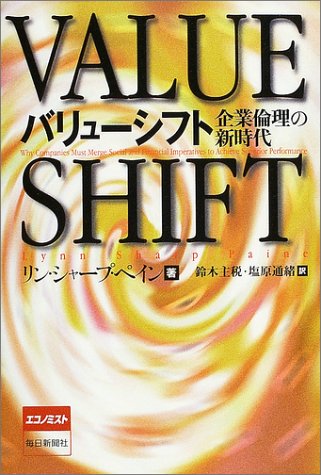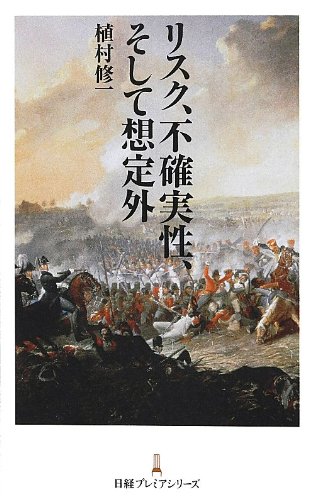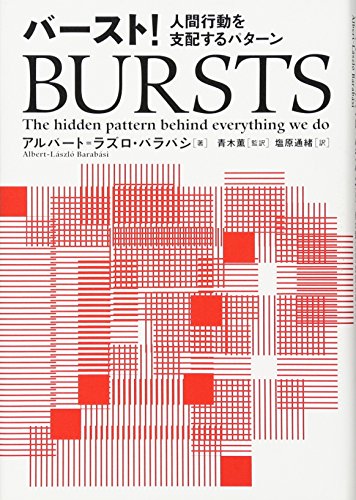●薫習(くんじゅう)
素敵な言葉だなあと、思わずメモしてしまいました。1)
平安時代の貴族たちが、衣服に香をたき込めたように、経験がしっとりと人格の中に浸透していくのを〈熏習(くんじゅう)〉というのです。
『顕識論』という本には、「香を焼くと衣服にその香りが浸み込んでいく。香はなくなっても、しみこんだ香気はいつまでも衣服に芳(かお)っている。熏習とはちょうどそのようなものだ」といっております。
「衣服に香をたき込めたように、経験がしっとりと人格の中に浸透していく」と書かれると、良い経験だけが都合よく浸透してくれるかのように思えてしまいます。もちろん、そうではありません。見た・聞いた・嗅いだ・味わった・触った・考えた経験のすべてがいやおうなく貯蔵されていくことを意味しています。
著者は薫習の概念を説明するために、洞山良介という中国の禅僧の言葉も紹介しています。こちらのほうが、経験がいやおうなく人格に浸透していくというイメージを持ちやすいかもしれません。
「ちょうど霧の中を行くようなものだ。衣服を濡らしたわけではないのに、いつの間にかしっとりと湿ってしまう」
「良い経験」と書きましたが、何が良い経験になるかは分かりません。病気や怪我など不如意なアクシデントでさえ良い経験だったと振り返ることができる、たくましい人もいます。
何が良い経験になるか分からないのなら、とにかく何でもたくさんやっておくのが合理的な戦略のように思えます。しかしもしそうなら、薫習という概念を奉じる大乗仏教の信者は坊さんになどならず、何でもやってみる修行を自分に課すでしょう。実際のところ、あの人は何十カ国を旅したことがあるから薫習の深い人格者だ、と単純にはいえなさそうです。
●経験に学ぶ
ここから先は、薫習という言葉だけを借りて、経験に学ぶことについて考えてみます。
旅は体験ですが、薫習されるのは経験です。経験とは体験と感情のセットです。体験の詳細はやがて忘れてしまいますが、そのときの状況と感情は、われわれの経験データベースに刻まれています。そしてわれわれがある状況を感知したとき、情動システムが経験データベースを検索し、過去似たような状況で起きた顛末(から生じた気持ち)を、情動としてわれわれに伝えます。
※ このあたりの考察は、過去の『「近道」的思考を磨く』などのコラムをご参照ください
たとえば人前で話をさせられて失敗して嫌な思いをしたとすると、人前に出ようとするたびにモヤッとしたものが胸をよぎります。このモヤッは当人の意図とは関係なく学習されたものですから、薫習といっていいでしょう。
さて、経験を感情を伴った体験の記憶とすると、いくつかの考察が導かれます。
一つめは、ひとつの体験が複数の経験の種となりえること。先の例でいえば、リアルな体験のときには嫌な思いをしたかもしれませんが、後で思い返しながら追体験をして「でもチャレンジする機会をもらえてよかった」という気持ちを持てたとします。一つの体験から相反するような感情が導かれたわけですが、これらは二つの経験としてカウントできると思います。つまり、体験の数だけでなく、それをどのように振り返るかによって経験の豊かさは変わるだろうということです。
二つめは、「脱薫習」というか、経験の浸透によって形成された人格の書き換えも、ある程度は可能だろうということ。記憶と忘却は同じメカニズムの表裏のように思えますが、人間が意図して行えるのは記憶だけであって、意図して忘れ去ることはできないといいます。いちど薫習されたものは永久に消えないのかもしれません。
しかし一方で、記憶を混乱させる効果的な方法は知られています。それは新しい記憶を重ねることです。とくに、すでに記憶していることと似て非なることを記憶しようとすると、それが以前の記憶に干渉して記憶が混乱する、つまり事実上の忘却が起きるそうです。
上記をまとめて、いやおうなく人格に染みこんでいく香りを、少しでも自分の望ましいものに近づけるための心得のようなものを考えてみました。
- こうありたい、こうふるまいたいというイメージを持つ(←望ましいイメージがなければ成功失敗の判断もない)
- 場数を踏む、つまり体験する(←体験がなければ経験もない)
- 体験のたびに、そのイメージに照らして成功失敗を振り返り、感情的に評価をする。つまり成功であれば嬉しい(もう一度やろう)と思い、失敗であれば悔しい(同じ失敗は二度としない)と思う(←この感情が経験データベースを築く)
- 失敗の場合でも、「こういう面では成功といえる」と限定するなどして、肯定的な感情も見いだす(←小さくとも成功がなければ望ましいイメージに近づけない)
- そのような肯定的な感情が持てるような成功体験を多く積み重ねる
(1) 太田 久紀 『仏教の深層心理』(有斐閣、1983年)より。いくつかの辞書にあたってみると、「熏」より「薫」が一般的に用いられているようです。わたしも薫のほうが香りを連想しやすいので、以下〈薫習〉と記します。ちなみに「熏」に火偏をつければ燻(いぶ)すで、〈燻習〉もよさそうに思いましたが、この用字例は辞書にはありませんでした。