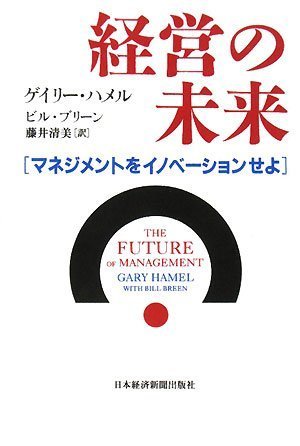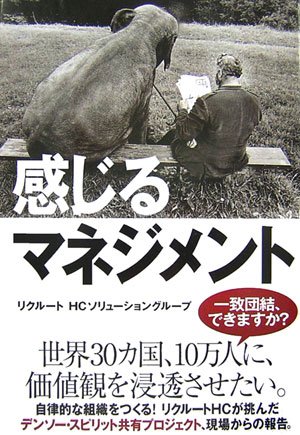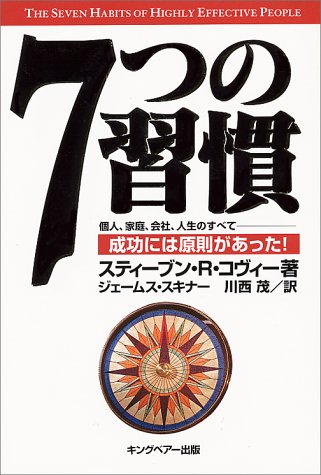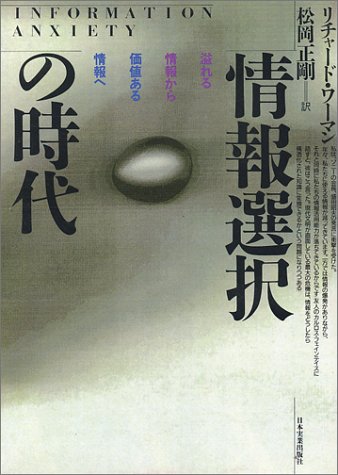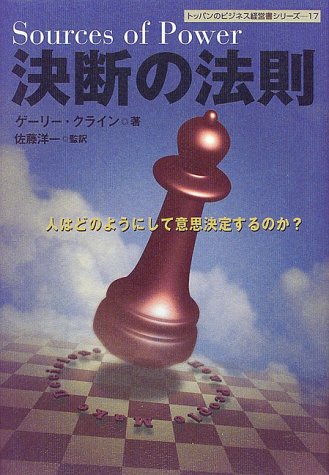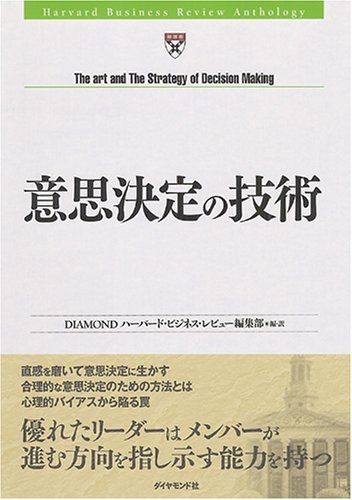「インテリジェント・デザイン」とは、『知性ある設計者によって生命や宇宙の精妙なシステムが設計されたとする説(Wikipedia)』のこと。個人的にはこの考え方に与するものではありません。しかし創造の過程はどうあれ、進化の結果としていま目の前にいる小さな昆虫などを見ていると「知性ある設計者」の存在を想像したくなる気持ちは分かります。自然や生命の仕組みはそれほどまでに巧みに思えます。
一方、組織は人間が作るものです。何万人の大企業であろうと、誰かが意図を持って仕組みを作り、運営しています。完璧ではありません。それにも関わらず、我々は組織が課してくるデザイン上の制約を、あたかも「知性ある設計者」が作りあげたもののように受けとめ、変えられないものであるかのように不満を言ったりしています。その仮想の制約に基づいて意志決定をしたりしています。例えば:
- 処遇に不満があるのに社内の誰にも相談せず、転職する。
- 「前例がない」からと、提案をあきらめる。
- 「そういうものだ」と、部下の不満を押し込める。
そういった制約の多くは、実際には社員よって支えられている幻想であることが少なくありません。
幻想とはいえ、強固なものです。ある企業の研修で、現場の制約をまったく外した「理想のプロジェクト」を定義してみたことがあります。結果は奇妙なものになりました。チームによっては、メンバーの希望を容れない人材配置や残業を前提にしたスケジュールなど、「現状の縮図」としか言えないようなプロジェクトになってしまうのです。
プロジェクトマネジャーは「期限内に終わらせるためにはどうしてもこのやり方が必要だ」と主張して譲りません。「それが本当に『理想』なのか」「全員の満足を最大にするにはどうすべきか」「自分が一メンバーであったらどうか」など、様々な角度から自問を重ねてもらうことで、ようやく「メンバーの希望を聞いて、制約とすり合わせる」といった新しいやり方を試そうという気持ちになります。
幻想に囚われていることは、他人事として見ている分には指摘しやすいものです。上で引用した企業に向かって、その「新しいやり方」は他の企業では既に「なじみのやり方」ですよ、と言うことは容易です。かもしれません。しかし自分自身の幻想、または自分がその一部となっている組織(家族・企業・社会など)の幻想を見極めることは、とても難しいものです。
よい意志決定の障害となるこの幻想を取り除くためには、少なくとも以下の2点が必要です。
(1) 判断基準となる「ありたい姿」を現状から離れて明確にすること
(2) 自分の思考や組織が「インテリジェント・デザイン」ではないことを肝に銘じること
このコラムでは(2)を強調したいと思います。組織も、しょせん人間の作ったもの。ゲイリー・ハメルは『経営の未来』の中でこう述べています。
近代経営管理は多くのものをもたらしてきたが、それと引き換えに多くのものを奪ってきた。そろそろこの取引について考え直してもよいころだろう。我々は。わずらわしい監督者の階層を築かずに何千人もの人びとの活動を調整する方法を学ばなくてはいけない。人間の想像力を抑圧せずにコストを厳しく管理する方法を学ばなくてはいけない。規律と自由が互いに排斥し合う関係ではない組織を築く方法を学ばなければならない。この新しい世紀には、近代経営管理の不幸な遺産である一見避けられないかに見えるトレードオフを超越することを目指さなければならないのである。(p9)