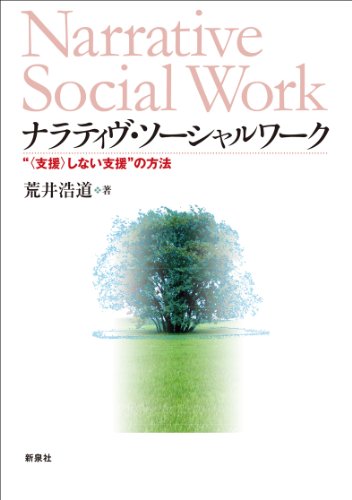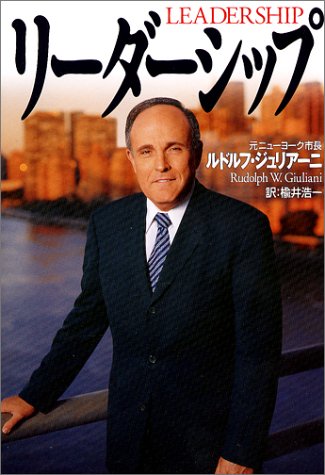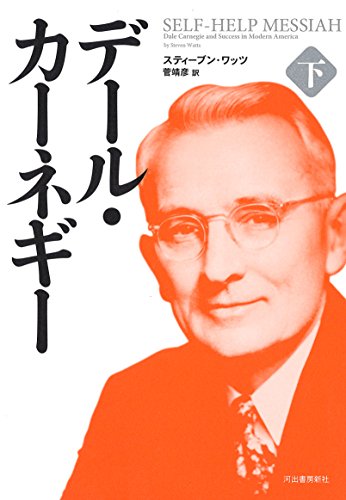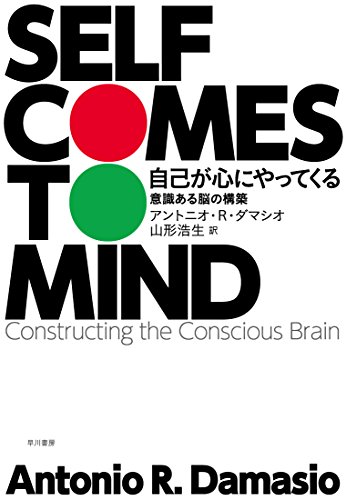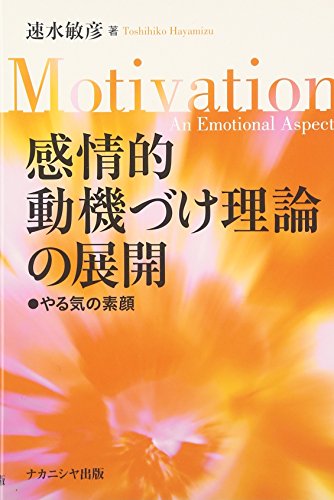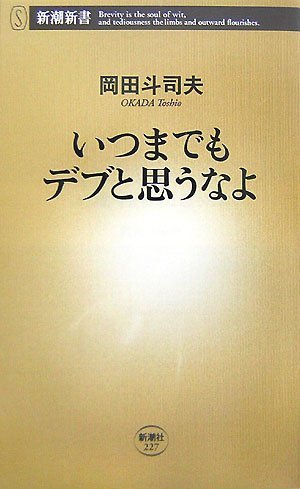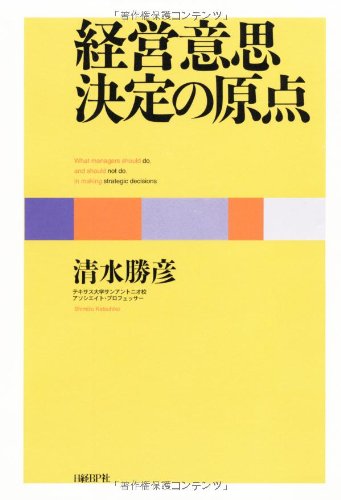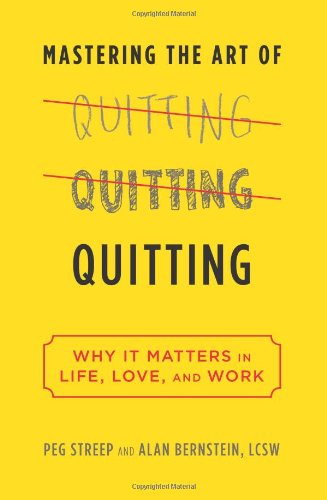【相談者だって自分の問題をよく理解しているわけではない】
問題を抱えた人の相談に乗るのは、奥が深い行為です。
「こうすればいいんだよ」という解決策(だけ)を示すのは、相談者(相談する側)の依存心を高めかねません。依存されるのは、相談に乗る側にとっては嬉しいことかもしれませんが、相談者にとっては善いとは限りません。
医者に依存しきった患者は、調子が悪くなるたびに先生に診てもらいたくなります。同じように、答えをもらった相談者は、それが素晴らしい答えであるほど、問題が生じるたびに答えをもらいたくなる誘惑にかられます。相談者に考えさせないことを目的にしているのでないかぎり、相談者のためになっているとは言いがたくなってしまいます。
そもそも、他者が当事者の問題をすべて酌み取れるわけではありません。「問題共有(Problem sharing)」では、複雑な問題を抱えた相手をどう支援するかというテーマについて書きました。
さらに、相談者だって自分の問題をよく理解しているわけではない。そのことに気づかせてくれたのが、『ナラティヴ・ソーシャルワーク―“〈支援〉しない支援”の方法』という本でした。
本書に、「“〈支援〉しない支援”の方法」の代表格であるナラティブ・セラピーを中心にしたアプローチが解説されている部分があります。以下、読書メモを兼ねてそのプロセスを紹介します。本書は総説ですし、わたしもソーシャルワーカーではないので、あくまでもわたしの理解を書き連ねたメモに過ぎないことを、おことわりしておきます。
【ナラティブ・アプローチで相手の相談に乗る】
0. 【無知の姿勢】相手の問題の原因に対して無関心を保つ (not-knowing)
ナラティブ・アプローチによる支援では、困難の「原因」を突き止め、その「原因」を取り除くことでクライエントが良くなる、とは考えないのです。
コンサルティングマインドの高い人は、手足を縛られたような気分になってしまうと思います。ナラティブ・アプローチは、社会構成主義という考え方に依って立っています。注意を向けるべきは、相手が問題をどう認識しているかという点であり、事象の因果関係を解き明かすことではないのです。
相談を通じて、相談に乗る側が持つべき姿勢という意味でゼロ番としました。1番以降は、厳密ではないにせよ、ステップと考えてよいでしょう。
以下のステップを学びながら、ある会社の社長さんから雑談がてら相談を受けたシーンを思い出しました。わたしの側には支援しよう(提案しよう)という気がなくハイハイと話を聞いていただけだったのに、お礼を言われたという思い出です。
1.【問題の外在化】問題を評価せず、「こだわっている物語」を整理する
善悪を評価せずに聞き、問題の整理に徹します。「こだわっている物語」(dominant stories)とは、相手がその問題をどのような物語として捉えているかを指す言葉です。dominantとは優勢な・支配的なという意味ですが、こだわっているとはなかなかよい訳語を考えたものだと思います。
その社長からは「うちの営業のできが悪くて困っている」という相談をいただきました。商品の中に、1年更新のサービスがあります。契約の終了時には報告会があり、社長はサービス提供チームだけでなく営業チームも出席させています。営業チームには、報告会の場でお客様の問題を聞き出したり、それをもとに追加提案をしたり、契約の維持・拡大に努めてほしい。それができないので、契約の更新率が上がらない。そういった相談でした。
わたしは(何しろ売る気がないので)「営業マンがうまくフォローできていないんですね」などと相づちを打つのみでした。社長も「そうそう、フォローなんだよ」などと応じます。
つまり「フォローができない営業チーム」が社長の「こだわっている物語」でした。
2.【例外の発見】「こだわっている物語」に現れる例外を発見し、「もう一つの物語」の存在を明らかにする
例外(ユニークアウトカム)とは、「こだわっている物語」にそぐわないエピソードなどのこと。そこに潜む「もう一つの物語」を明らかにすべく、(言葉によって)介入します。
営業チームへの悪口はしばらく続きましたが、ふと「言われたことはやるんだけどね」という言葉がありました。
悪口ばかりだったのでホッとして「言われたことはやると。たとえば……」と水を向けると、「提案書のひな形を作って送り出せば、手足を動かして新規開拓なんかはできる」との答え。
ここで社長の「もう一つの物語」、つまり「言われたことはやる営業チーム」が明らかになりました。
3.【物語の調整】「もう一つの物語」を整理し、相手が問題を「複雑な物語」として理解することを支援する
「複雑な物語」とは、問題は「こだわっている物語」でもあり「もう一つの物語」でもあるということです。
社長はすぐに「ただ、手足は動いても頭がね……」と、悪口に逆戻りしてしまいました。
せっかく営業チームの良い面が出てきたので、もうすこし引っ張ろうと考えて 「具体的な指示があれば、実行できる営業チーム。それだけでもうらやましがる社長さん、多いと思いますよ」と蒸し返してみると、 「んー、まあね。贅沢は言っていられないんだけど、ウチの場合はそれだけじゃね……」 と、考え込んでおられました。
わたしが相変わらず「そうですよねー、難しいサービスですからねー」などと相づちを打つうちに会話は収束しました。社長は「ありがとう、スッキリしたよ」と会話を締めくくってくれました。
その後営業チームの話をしたことはありませんが、事業は順調に伸びているようですので、自己解決されたようです。
【で、何が起きたのか?】
あらためて振り返ってみると、不思議です。社長の問題は当初より「複雑な物語」になったのに、なぜ「スッキリしたよ」と言ったのか。実際の会話は以上でおしまいでしたので、ここからはわたしの想像です。
物語が複雑化したというよりは、問題を多面的に捉えるきっかけを得たのだと思います。「フォローができない」けれど、本来「言われたことはやる」チームだという物語は、社長に「何をやるべきなのか、営業チームに十分伝えていないかも」と気づいた。それが「スッキリ」の正体だったのではないでしょうか。
社長は創業者で、今の営業チームを自ら採用し、育成してきました。そして新規開拓を一緒にがんばってきました。しかし今、新規開拓より既存顧客への深耕が重要なテーマとして浮上しています。社長にはそれが見えており、やるべきことは明らかです。それなのに営業チームはやるべきことをやっていない……。
「そうか、すこし高望みをしていたようだ」 社長は手帳を開き、タスクを書き出したことでしょう。
- 事業環境の変化に伴って必要な営業スキルも変化したことを共有する
- 新しい営業プロセスを定義する
- 営業チームが実行できるようなマニュアル化を図る
- 実行にあたり能力が足りないところはトレーニングで補う
……この読みにしたがって4.についてタイムリーに提案をしてトレーニングの仕事をもらった、というオチがつくと収まりがいいのですが、事実はただ雑談の相手をしただけでした。